News
今月のおススメ本は、久田恵著『ここが終の住処かもね』潮出版社

都会から離れた自然の豊かなところにあるサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)「ピラカンサ」。そこでの暮らしを綴った小説である。主人公はフリーライターのカヤノ。シングルマザーとして娘と息子を育て、一人前にした。だからサ高住の入居は、子どもたちから自分勝手だと言われようと、「老いてやっと究極の自己中心を生きる自由を得た母さんの権利でもある」といって決めた。いわゆる、アクティブ・シニア。著者のプロフィールを知る読者であれば、カヤノのモデルが久田恵さんであることは、容易に想像がつくだろう。
日々の生活でカヤノがつぶやく言葉やカヤノが聞かされる言葉は、ちょっとした箴言だ。いわく「とりわけ年を重ねていくと、そうすべきだ、そうしたい、と思うことも、実行する気力や体力が追いついていかなくなる」、いわく「人の家族のゴタゴタを聞いても、愚痴を聞いてもあまり心が動かない」、いわく「そ、人は期待しても無駄。たいてい裏切られる。期待に応えてもらえるのはまれ。自分の思うようにはいかない。そもそも人は変わらないってことをまず知らなきゃダメ」などなど。ある種の諦観をもって入居者たちと接しているからか、カヤノは人間関係にタフなのだ。と同時にのんびりした性格が人を引き寄せる。
「ピラカンサ」からほど近い丘でたまたま知り合った初老男性の風間と、「ピラカンサ」では他の入居者との交流も少なく、小さな庭で花を育てているまどかとの交流を通して、カヤノは2人が若いころ別れざるをえなかった恋人同士だったことを知る。そしてまどかとこんなふうに語り合う。
まどか「でもね、あんまり昔だから、きっと天国で会っても分からないと思う。でも、会えなくてもずっと心の支えだったからすごく感謝しているの。私は、ここにずっといて、シアワセだったし、守られていたから」
カヤノ「守られていたって、その方に?」
まどか「正確に言うと、その人と過ごした時間の思い出にかな」
静かに、さらり、そして深く。自分と折り合いをつけながら年齢を重ねきた人の言葉が沁みる。
登場する人々の悲喜こもごものエピソードの一つひとつは小さなものかもしれない。しかし、どれも当事者にとっては切実であり、それらを躊躇しながらも受けとめ、ときに翻弄されるカヤノの姿を通して、読者に人生で大切なことが伝えられる。
ちなみに生活がなかなか落ち着かず、何かと心配だった息子の亮介くんも、ひとり暮らしの高齢者のニーズに寄り添った新しい事業を立ち上げた。よかった。(芳地隆之)
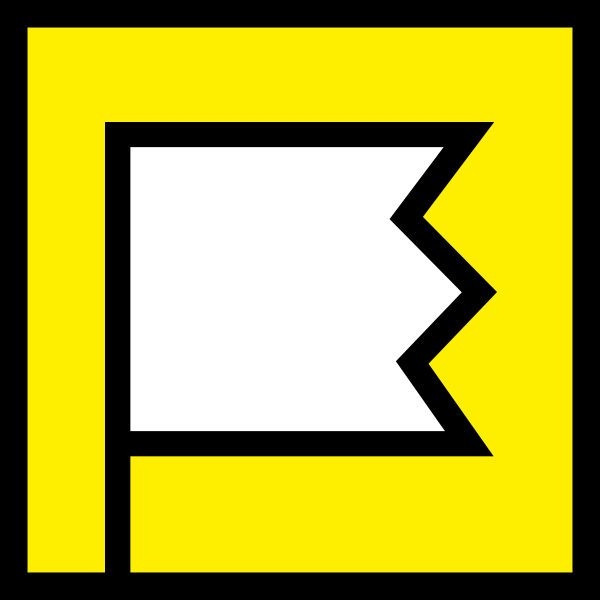





-scaled.jpg)