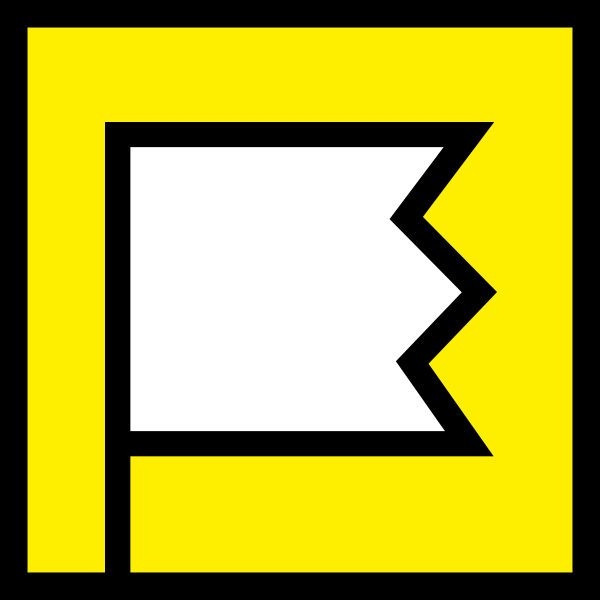News
今月のおススメ本は、宮嶋勲著『最後はなぜかうまくいくイタリア人』日経ビジネス人文庫
.jpg)
「私が専門であるワインの世界で言えば、醸造責任者なのに英語がうまいから外国に頻繁に行って輸出部長のような仕事をしている人とか、栽培担当なのに機転が利いてチャーミングなのでレストランを手伝っているといったような人たちだ」
日本とイタリアを往復し、ワインと食について執筆活動する著者が、イタリア企業における働き方の一例を挙げている。家族経営の中小企業が多いこともあろう(フェラガモやベネトンもそうだ)。全体像が見えて、自分がすべての工程に関われる、職人的な仕事であれば、「自分の役割は〇〇です」と職務を限定することなく働くのである。
イタリア人は、この仕事が自分のものであるという感情をもてると抜群の能力を発揮するという。フォードのような同品種のモデルを大量生産する自動車メーカーよりも、一台、一台に個性が現れるような車をつくるフェラーリが生まれる土壌があるのだろう。
同国の公共サービスの質と効率がよろしくないのは分業制で働く職場だから。「自分のものであるという感情」がもてないと、テキトーに仕事をするようになるのである。ワークライフバランスよりも、仕事とプライベートの境が曖昧な方がいい。家族経営が向いているのは、互いの顔が見えるから。国家よりも自分たちの地域や家族に信頼を置くことの究極がマフィアの世界へとつながるのかもしれない。
計画を立てても、それが計画どおりにいかないことを前提としているかのように動く。途中で寄り道しながらも、なんとか最後はつじつまを合わせる。その寄り道が新しいアイデアを生むきっかけになる。計画は計画通りに進まないという「不測の事態を常に予測している」姿勢でいるからこそ、それによって生じたピンチにも動じることなく、臨機変に乗り越えていくのだろう。好きなことはすぐに始めるが、嫌いなこと(でもやらなければならないこと)を後回しにするから、事態がややこしくなるのだが、短所を改めるくらいなら、長所を伸ばす方がいいということなのだ、たぶん。
こうしたイタリア人の特徴を一言で表すと本書のタイトルになる。困りごとは周囲にさらけ出そう。「裸の自分を見せて、相手の懐に飛び込む」ことが評価される国。イタリア人が楽しそうに見えるのは、「最後はなぜかうまくいく」からなのだ。 (芳地隆之)