Topics
DOではなく、BEでいられる場所~コロナ禍を経て見えてきた生涯活躍のまちが目指すもの~
.jpg)
当協議会の月刊小冊子『生涯活躍のまち』過去の記事の配信。今回は37号掲載の前消費者庁長官・伊藤明子さんのインタビューです。伊藤さんが国土交通省から内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局に出向され、事務次長に就任したのは2014 ~ 2016年でした。地方創生が始動したころです。その後、国土交通省住宅局長などを経て、再び同本部事務局で地方創生総括官補を務められたのが2018 ~2019年。生涯活躍のまちをはじめ地方創生に直接関わったのは3年ですが、その後、消費者庁長官として、とりわけコロナ禍において見えてきた課題について、ダブル介護をされてきたご自身の経験も合わせてお話しいただきました。とても示唆に富む内容になっています。じっくりお読みください。
伊藤 明子(いとう あきこ)さん
前消費者庁長官/公益財団法人住宅リフォーム紛争処理支援センター 顧問/株式会社まち・ひと・しごと研究所 代表取締役
1984年建設省入省。2014年内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長兼内閣府地方創生推進室次長、2017年国土交通省住宅局長、2018年内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補などを経て、2019年消費者庁長官に就任。2022年退職。
コロナ禍がもたらしたもの
コロナ禍によって私たちは世界とつながっていることを実感させられました。たとえば、中国における生産活動の停滞がサプライチェーン(供給網)に影響を及ぼし、私たちの家庭にあるウォシュレットの部品が届かなかったといったこともあれば、デジタル技術が進展し、間接的に様々な人とつながるようにもなった。自分のためにと考えて行動することが他者にとっての利益につながる――それを指摘したのはフランスの経済哲学者、ジャック・アタリさんです。彼は、自分がコロナに感染しないように気をつけることが、自分が他人にコロナを感染させない、ひいてはパンデミックの抑制につながることを「合理的利他主義」と呼びました。日本語でいうところの「情けは人のためならず」でしょう(最近はこの言葉を「だから人に情けをかけてはいけない」と捉える人が半分くらいいるとのことですが)。
一方でその限界も知りました。人は直接会わないとわからないことがある。外出から汗かいて帰ってきたな、とか、ほこりだらけになっているけれどどうしたのだろう、とか。とくに初対面の場合、「この人は信用できるのだろうか」をオンラインでは判断できませんよね。他者に対する非寛容も広がりました。たとえば、「マスクがないのはけしからん」と誰かを悪者にしなくてはやっていられないというような風潮です。
孤独・孤立の問題
生涯活躍のまちの考え方は高齢化の文脈のなかで生まれたわけですが、消費者行政に携わることで、孤独・孤立の方がより問題であることが見えてきました。わが国における世帯構成の比率は、1980年には全世帯に占める「夫婦と子」世帯が42%、祖父母を含めた「三世代」世帯が20%、単身世帯が20%でした。それが40年後の2020年には、単身世帯が38%、「夫婦と子」世帯が25%、「三世代」世帯が7%と大きく変わっています。
これを消費者行政の視点からみると、悪質業者からの電話がかかってきても、「それ変じゃない」と指摘する家族がいないことで被害の拡大につながる。高齢者だけの問題ではないのです。
「フィルターバブル」という現象をご存知でしょうか。ネットでいろいろな商品を見たり、購入したりしていると、「あなたはこれが好きでしょう」といろいろなモノが提示される。本来、情報の共有は体験の共有にならなければならないのに、インターネットの検索サイトが提供するアルゴリズム(Googleなどの検索エンジンが検索ワードに対して検索結果の順位を決めるための基準や方法)が見たくないような情報を遮断する。すなわち情報によって囲い込んでしまうのです。するとどうなるか。人は自分の嗜好のなかで孤独になっていきます。コロナ禍では、若者の方が家にこもりがちだったので、そこで生活が完結し、身体性が欠如する。Chat GPTにいたってはフェイクかどうかの判断もつきかねません。よほど自分のなかに確固たるものをもっていないと、自分が主体的に考えているのか、何かに思い込まされているか、わからなくなるのです。
日常が戻りつつある現在、コロナ禍がもたらしたもののうち、何が普遍で、何が戻って、何が変わっていくのか。それを検証することで、生涯活躍のまちの目指すものが鋭角的に見えてくるのではないでしょうか。
空間価値、空間資源
生涯活躍のまちでは、増加する空き家や空き地の利活用も大きな課題として取り上げられました。私が現在取り組んでいる団地再生についていうと、これまでは、郊外に住んで都心の職場に通うという職住分離が進められてきました。合理的に機能を切り分けて、「これがいいまちづくりだ」と思って進めてきたわけですが、共働きが増えるにつれて、団地は団地、あるいは戸建ては戸建て、と同じような世帯や収入の人が一緒に住み、同じように年齢を重ねていった結果、地元の小学校が廃校になるといった事態も生じているのです。
国土交通省では1966年に住宅建設計画法が制定されました。高度成長期の大都市への人口集中による住宅不足を解消するため、住宅の建設を推し進めるというものでした。私自身も住宅局で取り組んでいたのですが、2009年には住生活基本法に変わりました。建物というハードではなく、生活というソフトを主体に。プロダクトアウトからマーケットインへ。「この商品をどう売ろうか」ではなく、「暮らしのなかで必要なものは何か」を考えましょうとなったのです。
こうした変化は消費のありかたのそれと無関係ではありません。すなわち、モノ消費→コト消費→トキ消費への流れ。これはbuy → do → be とも言い換えられるでしょう。うち、be とは何か。誰かがあなたに何らかのサービスを提供するということではなく、たとえば、ただのんびり海を眺める。そこで何かをするのではなく、どこで誰といるかを大事にする。空き家・空き地では、そこにある記憶も大切な要素になるかもしれません。
先日、佛子園の施設を訪問したときに感じたのは、視界の片隅に誰かがいて、その同じ空間に自分が身を置くことの心地よさでした。別に交流したり、お世話をしたりしなくてもいいのです。ぼんやり周りの風景を見ることで発見できることもあるわけで。
60歳以上の単身者が頼れる人は誰かについて、各国の比較をみると(内閣官房孤独・孤立対策担当室「孤独・孤立に関連する各種調査について」2015年より)、日本では別居家族がトップで67%(米国56%、ドイツ63%、スウェーデン58%)でした。友人となるとがくんと下がって21%(米国48%、ドイツ46%、スウェーデン49%)。欧米にはキリスト教をベースとしたクラブ社会=サードプレイスがあるからではないかと思いますが、日本では、家族に頼るとはいえ、単身世帯が一番多くなっているのにどうするのか。佛子園型の施設は日本式のサードプレイスになるのかもしれません。和室がそうですよね。ここが食事するところ、ここが寝るところと空間が用途によって分けているわけではない。それによって感じる居心地のよさは、空間のデザインとはちょっと違う、「空間力」と呼んでもいいでしょう。
個人の生活で思うこと
私には障害のある娘がいます。この4年間は認知症の父の介護もしていました。父はつい最近、グループホームに入所したのですが、それまではダブルケアの日々でした。
父はコロナ禍の早い段階で感染し、ホテルで隔離するか、自宅療養をするかの判断を迫られました。その際に考えたのは、「人とのつながりが切れて、誰にも面倒をみてもらえずに亡くなるのか」「コロナによって命を落とすのか」。もし父をホテルに住まわせたら、一人で食べることはできません。ひとりきりでいたら欝になってしまうでしょう。私は自宅での療養を選択しました。
父には、娘が座る車椅子を通所サービスの迎えが来る際に押して車に乗せるという役割がありました。私のことはよくわかっていなかったけれども、孫には自分なりのケアをしていた。その姿を見て、人は誰かに必要とされることがいかに大切なのかを教えられたのです。
障害のある娘をいない方がいいと思ったことは一度もありません。そこにいてくれるだけでいい。何かをするという activityではなく、先ほど申し上げた、誰とそこにいるかという be なんです。
(ダブルケアをしながら仕事をすることは大変だったのでは、との問いに)私の場合、子どもに障害があったことで、常に生活があり、足に重りがついている分、地球の中心と結びついているという感覚がありました。国家公務員の仕事は物事が抽象的になりがちです。そうしないと制度はつくれません。したがって鳥瞰的な視点が必要とされるのですが、娘や父がいるおかげで、肌感覚をもちながら取り組んでこられたと思っています。
本当の多様性とは何か
DE(I Diversity=多様性、Equity=公平性、Inclusion=包括性)のうち、Divesityでは女性活躍と国際化に焦点が当てられがちです。女性活躍について、たとえば大学進学率をみると、全国における男女のそれはほぼ同じですが、地域別になると、東京都の女性の進学率が70%であるのに対して、鹿児島県のそれは半分になっています。鹿児島県が東京都に比べて低いのは、近くに大学がない、大学を卒業しても働くところがない、経済的負担が大きいなどの理由が考えられるでしょう。東京と地方では女性の非正規雇用の比率も違い、東京は正規採用の割合が高いから人が集中する。国内でもこれだけの違いがあることは理解されているのでしょうか。
その壁になっているもののひとつがアンコンシャス・バイアス(unconscious bias)、「無意識の偏ったものの見方」です。「女の子なのでランドセルの色は赤」とか、「女性は理系に弱い」とか。それによってガラスシーリング=ガラスの天井で覆われる。女性たちがそう言われ続けることでつくられる「ガラスの天井」を破るための議論をしていく必要もあるでしょう。
“WeThe15”という、スポーツ、人権、政策、コミュニケーション、ビジネス、芸術、エンターテインメントといった分野の国際組織が結集し、発足したグローバルムーブメントがあります。世界の人口の15%、すなわち12億人には障害がある。つまり、障害のある人は特別な存在ではなく、インクルーシブな社会の一員なのだという考え方を広める運動です。
ただし、人を抱き込むためには強くなければなりません。
多様性を進めれば、トラブルも増えます。これまでの社会はそれを回避するために、組織を縦割りにしてきました。私はよく「シャッターガラガラ」と呼ぶのですが、役所に何かの問題が持ち込まれた際に、「それは私たちの所管ではありません」とシャッターを下ろしてしまう。いったん受け止めてから「できません」というよりも楽だからです。しかし、いまその場で自分の役に立たなくても、後々になって「ああ、そういうことか」と思うこともある。それが人としての土壌を豊かにするのであるから、水は深いところから汲んだ方がいい。そう思って、役所にいるときから、なるべくシャッターを下ろさないように気をつけていました。
なぜDEIについて話したかというと、SDGsの理念である「誰一人取り残さない」に、強さをもっている側が弱い側に何かをしてあげるというニュアンスを感じるからです。むしろ「お互い取り残されないよう気にかけよう」ではないか。
ごちゃまぜは、誰が上で誰が下でということはない、フラットでいるための手法だと思います。「ごちゃまぜにすれば、何かが生まれるだろ」と。それがいいと思います。
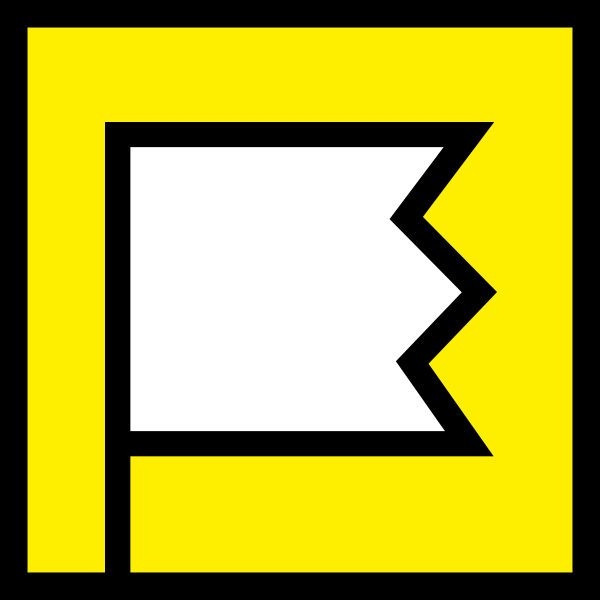




①.jpg)

