Topics
特集:新しい生活様式?

新型コロナウイルスの感染が初めて国内で確認されて1年以上が過ぎた。
「この間、名刺がぜんぜん減らなかった」というのは社会福祉法人愛知たいようの杜の大須賀豊博理事長(当協議会副会長)である。コロナ禍以前は愛知たいようの杜が運営する「ゴジカラ村」への視察が全国から相次いでいたため、名刺交換をよくしていたのだが、その流れがぱたりと止まった。ゴジカラ村内には高齢者施設もあるので、いま発症させてはならないと緊張が続く毎日だ。
子どもから高齢者まで様々な世代が交ざって暮らすことを実践してきた「ゴジカラ村」は、いままでにない試練と向き合っている。そんな中でも、もりの幼稚園に子どもを預けにくるお母さんたちが、高齢者施設の入居者に少しでも喜んでもらおうと、ちょっとした工夫をするさまに気持ちが温まる。
Go to トラベルで一気に高まった観光需要が、感染の急速な拡大を受けて休止になるという乱高下を経験した日本旅行の渡邉さんは、業界のなかで一喜一憂するのではなく、旅行会社として自分たちに何ができるのかを模索している。そして、その答えを教育とSDGsに見出した。
長野県佐久市の地域おこし協力隊を経て起業した加藤夕紀子さんは、コロナ禍によって首都圏から地方への人の流れができつつあることを実感している。東日本大震災によって自らの価値観が変わり、生活と仕事の場を東京から長野に移した加藤さんは、リモートワークが当たり前になった現在、生活の豊かさを考えれば地方に住まうほうがプラスであり、働き方が変われば、生活も変わるという。
物理的な距離を保ちながら、心の距離をどうやって近づけていくか。Social distancing と Heartwarming の両立は、言うは易く行うは難しだが、「密」は不特定多数が行きかう、集まるところで生じるものだ。気心知れた者は不自然に身を寄せあったりしない。かつて玄関先や縁側で茶飲み話をする人たちの間には適度な距離があった。お辞儀も、お互いが頭を下げ合ってもぶつからない間合いの取り方だ。
新しい生活様式とは昔の生活様式を取り戻すことなのかもしれない。だから今回のタイトルに「?」をつけた。大須賀理事長は、近代100年かけて快適さと便利を追求したことがコロナウイルスの蔓延につながったのだとしたら、そこから戻るのにも100年かかるのではないか、という。ならば、ゆっくり私たちの暮らしを見直してみてはどうだろう。その途中でこれまで見過ごしていた新たな発見があるかもしれない。

子どもから高齢者まで多世代が交ざって暮らす「ゴジカラ村」が新型コロナウイルスの感染拡大により、それがままならなくなって1年以上が過ぎました。高齢者施設で感染者を出してはいけない――「ゴジカラ村」を運営する(社福)愛知たいようの杜の大須賀理事長(当協議会副会長)は日々、細心の注意を払いつつ、人と人とのつながりが断たれてしまっていることに心を痛めています。ただ、一方で周りの人たちやスタッフによる入居者の寂しさを和らげる試みも。様々な制約のなかで自分たちは何ができるのか。それを考えることで見えてきた「いいこと」についても語ってもらいました。
*
お年寄りが子どもの顔を忘れてしまう
私たちは人と人とのつながりを大切にしてきました。高齢者施設のなかに子どもたちが遊びにきたり、そこで家族も一緒に楽しんだり、ボランティアの方が手伝いにきてくれたり。施設に暮らすお年寄りもそうですが、これまでゴジカラ村に来てくれていたのに来られなくなった人たち——やりがい、生きがいを感じて手伝ってくれていた人たち——が今どうしているのかも心配です。
現在、高齢者施設に外部の人間は一切入れません。家族との面会は衝立越しで、時間は15分くらいに制限しています。そうすると入居しているお年寄りがご家族の顔を忘れてしまうことがある。息子さん、娘さんが本当に悲しそうで、こちらも辛い。本来なら家族が「おとうさん」「おかあさん」あるいは「おじいちゃん」「おばあちゃん」と手を握って、「大丈夫?」と声をかけてあげるのが何よりなのですが……。
一方で家族のつながりも
当法人で働く職員は基本の健康チェックは怠っていませんが、施設で新型コロナが発症しないよう、彼ら、彼女らの意識をより高めていくよう努めています。何かひとつでも緩むと、ウイルスをもち込んでしまう。職員には若い人が多く、普段であれば仕事の後、まちなかに食べに行ったり、飲みに行ったりすることもあるし、名古屋など都市部に買い物に行くこともある。しかし、いまそれをやると、ウイルスを拾ってきてしまうかもしれません。
たとえば3世代で住んでいて、20代の孫がアルバイト先や飲食時に感染し、ウイルスを家に持ち込んでしまったとします。家族は14日間外出禁止。生活物資の調達が難しくなる、地域の目も厳しくなる。しかも、そこに介護が必要なおじいさんやおばあさんがいたら——みんなが大変な思いをするのです。
介護施設で感染者が出ると、病院のように、レッドゾーン(感染者)、イエローゾーン(防護服の着脱)、グリーンゾーン(非感染者)とゾーニングしなければなりません。介護施設の職員も感染予防の知識をもっているので、医療従事者と同じくらい強いストレスを抱えながら日々働いています。昨年の緊急事態宣言解除後の感染拡大が少し落ち着いてきた昨年夏、私は「『Go to トラベル』キャンペーンでも使って、いまのうちに出かけておきなさい」と職員に外出を促しました。秋冬になると感染者が必ず増えて、職員は絶えずプレッシャーに晒されるだろうから、いまのうちに気分転換をと思ったのです。
感染が再び拡大した12月初旬からはストップをかけました。1月に入ってからは全員、マスクを布製やウレタンから不織布に交換。飛沫が飛散する量を抑えるためです。
私たちは職員に厳密に指導していますが、施設入居者の家族の行動までは把握できません。長久手市では若者の感染者が多いと言われているのですが、感染していても症状がひどくないと、黙って部屋にいるケースもある。私の義父であるゴジカラ村の創設者、現在は長久手市長である吉田一平は、愛知県内で最初に成人式の中止を決断した首長になりました。周囲からは少なからぬ批判も受けましたが、吉田は介護事業に取り組んでいたので、感染の怖さをよくわかっているのです。
私は3世代、9人家族で暮らしているのですが、家に戻ると毎日このテーマで話し合いをもちます。法人内ではいろいろなつながりが切れてしまっている一方、同居家族と話す機会がとても増えました。

交流を維持できた建物の構造
施設の建物のなかには入れませんが、高齢者施設は外に向かって大きなガラス張りになっているので、ガラス越しで面会をする家族もいます。そうであれば時間の制限はありません。ガラスの向こうには子どもたちが走り回っている姿や、施設の建物に面している公園に近所の方が散歩しに行く姿も見えます。この前は、(ゴジカラ村にある)もりの幼稚園に子どもを預けているお母さんたちが、高齢者が寂しそうなのでと、中庭で沖縄の三線を引いてくれました。施設内で歌を歌ってくれていたボランティアさんたちも、外から声を届けようと中庭で歌を披露してくれました。寝たきりになった入居者にも声は届きます。部屋の向こうに誰かがいることを感じられる建物のつくりにしたことが、いまとても活きています。
ちなみに建物のなかには縁側があります。普通、縁側は外に向かってつくられますが、それを施設のなかの廊下側に設置しました。部屋の廊下側の窓を開けると、そこが縁側になっていて、廊下を行き来する人と話しができる。お互いが適度な距離を保って語らい合う空間です。
高知市の「沢田マンション」という集合住宅をご存知でしょうか。鉄筋コンクリート建築を専門職として手掛けたことのない夫婦が子どもと一緒に建築したもので、普通のマンションは玄関側に住人用の通路をつくるのに対して、沢田マンションではベランダ側に通路をおき、ベランダと通路で住人が顔を合わせるようにした。住人はベランダに干してある洗濯物をかきわけて自分の部屋へ入るわけですが(笑)、あえて縁側的なつながりをつくったのです。
暮らし方は変わるのか
昨年の緊急事態宣言のときは、みんながすいぶん自粛しました。24時間営業していた飲食店も営業時間を短くしました。そうしたら、24時間お店が開いていなくても、暮らせることがわかった。リモートワークが当たり前になって、満員電車で仕事へ行かなくて済むこともわかった。
いいことと悪いことは表裏一体です。「いいとこどり」はできません。新型コロナウイルスは、輸送手段が発達し、短時間で長距離の移動が可能になった世界だからこそ、広まってしまった面があります。それによって地域のつながりは絶たれてしまいしたが、一方で家族のつながりが深くなったところもある。雑木林を緑豊かにしたら、その分虫がたくさん発生したというのと同じです。いいことの横には悪いことが、悪いことの隣にはいいことが隠れている。にもかかわらず、みんないいことばかりを享受しようと考えるから、その反動に苦しむのです。
昨年の緊急事態宣言が解除された後、「あれば便利だけれども、なくても大丈夫なモノやコトがたくさんあること」にみんなが気づいたはずなのに、生活スタイルはもとに戻っていきました。「いいとこどり」はなかなか捨てられないのを見て、「100年かけていまのような便利な暮らしを手に入れた人間は、それを手放すにも100年かかかるのかな」と思いました。

わざと不便に
最近は何でもリモートで済ませてしまう傾向が強くなりました。研修や講義はリモートでも対応できるでしょうが、会話は遠さを感じてしまう。私たちの法人では、人数は最大5人まで、時間も短くという条件で、職員はなるべく対面で会議をするようにしています。
リモートを使って(高齢者施設に入っている)お年寄りと家族が面会することは、技術的には可能です。しかし、そうすると、家族はそれでお年寄りと会った気になってしまう。それが便利となったら、「部屋にカメラを置いて、いつでも様子を見られるようにしてほしい」とも言われかねません。それではあまりに寂しいし、介護職員の監視にもつながってしまいます。したがって、これからもなるべく衝立での面会を実施していきたいと思っています。
私たちは強制的に家族が施設を訪れるルールをつくってきました。たとえば週1回もしくは月1回、家族が施設に来て、部屋の清掃をすること。一般的に高齢者施設の入居者の部屋は職員が清掃しますが、当法人ではこれができなければ入居は断っています。それぐらいしないと、来ない家族もいるからです。
いまはコロナ禍で家族による掃除は実施できませんが、代わりに家族にマスクをもってきてくださいとお願いしています。法人内でもマスクを販売することはできるのですが、あえて家族にもってきてもらう。そうすると、職員と家族の関わりもできるようになります。
人との関わりをどうやってつくっていくか。コロナ禍でそれを考え続けることで、私たちは大事なことを学べる。この1年でそんな思いを強くしています。

名古屋教育旅行支店の支店長として教育事業への新たな提案に取り組み中。
日本旅行は2016年に地方創生室を開設して以降、分野横断的な活動を展開。昨年来の新型コロナウイルス感染拡大で難しいかじ取りを強いられているなかでも、これまで培ってきた他業種との連携の経験を生かして、現状を乗り越えようとしています。その鍵はSDGs。それはどうしてか。広い視野をもってビジネスに取り組む渡邉さんの視点からはたくさんの考えるヒントが読み取れます。
*
――渡邉さんはコロナ禍にもかかわらず、いろいろな提案をされています。(独法)国際協力機構(JICA)、(公社)青年海外協力協会(JOCA)との連携による「KOMAGANEグローバル人材育成プログラム」※もそのひとつだと思います。
※JICAの青年海外協力隊訓練所ならびにJOCAの本部は長野県駒ケ根市にある。
JICAの青年海外協力隊経験者が中心となっているJOCAが、海外で貢献される方に向けたプログラムをつくっていることを聞いて、これは教育旅行に必要な案件になるだろうと思いました。現地で語学を習得するだけなら、海外の語学学校に通えばいいわけですが、向こうに行って気づきをもつこと、語学研修を通じて海外の異文化を学ぶことは、自分の視野を広げることにつながります。
人口が減少していくなか、海外で貢献したいという志の高い人のJICA海外協力隊(青年海外協力隊/シニア協力隊)への応募も年々減っているそうです。ならば高校生が将来応募するように、あるいはすでに社会人になった方が何かのタイミングで参加することにつながるようにしよう。学校の先生方と話していて気づくのは、JICA海外協力隊経験者や、これから行こうと考えている方が意外と多いということ。そうした気持ちを若い世代に伝える機会をもっと広げないと、日本の国際貢献活動は立ち消えてしまいます。
――どのような方向性のプログラムですか。
まずはコミュニケーションツール。言葉のわからない国へ行くのに、とにもかくにも必要なものです。そして現地での社会貢献につながる提案を考えています。昨今、SDGsがいたるところで叫ばれています。今年は行動の年と位置づけられていますが、欧米からは、日本のSDGsは行政主体で、企業や市民団体の動きが弱いとみられています。であれば、なおさら学校の先生たちに弊社のプログラムを説明し、理解いただければ利用してくれるのではないかと考えました。
ある県の私学協会の理事長と話した際、私学経営という観点から、教育プログラムとして、JICAやJOCAの活動に関心を示しておられました。私学の経営者の皆さんが集まる研修会でJOCAの方に講演をしてもらおうと思っています。そうすれば、先生方の関心も一気に高まるのではないでしょうか。
広報活動をしっかりしておかないと、いくら企画書をもって行っても物事は進みません。駒ケ根市にはいい資源があるので、あとは伝える努力だけなのですが、JOCAの方は広げ方がわからないとおっしゃる。ならば広報は私たちが担おうと伝えました。
JICAは独立行政法人なので、特定の民間企業に肩入れすることはやりにくいかと思います。JICAとしては将来のJICA海外協力隊員の減少を危惧していることから、私たちの方で、駒ケ根市、JOCA、日本旅行の3者で行う企画書をつくった次第です。

――人の流れづくりという観点からお聞きします。関係人口を増やしていく、とくに企業が社員を一定期間、地方に送り込み、リモートワークや地域での活動に従事させる「逆参勤交代」のような仕組みをつくっていくためには、何が必要だと思いますか。
クリアすべきは会社の総務規定や現地に行く場合の制度設計、本当に地方で仕事が成り立つのかなどです。弊社も昨年12月より八丈島において何人かがリモートワークの実験をしていますが、それが機能するには、社内制度が確立され、助成金など国からの支援がないと難しいのではないでしょうか。
社員が地域に行って自社の仕事をしているだけでは意味がありません。その地域で貢献できるものは何か。その企業ならではのものを使って地元で活躍できる人、そうした人材を育成するプログラムを現地で行うのもいいでしょう。「社員のメンタルヘルス対策」もありえると思います。人とのつながりが苦手な人や精神的な面でいろいろ負担を感じている人たちが、居場所を与えられることで変わっていくかもしれません。
あるいは「地元と企業に〇〇なメリットがある」研修ミッションを各企業がつくっていく。コロナ禍で経済的に不安定な企業もあるので、ある程度限られてくるでしょうが、各業界が持ち回りでできればいい。あとは横の連携をどう広げていくか。自分が参加したものに別の企業の人が来て意見交換すれば、次回は一緒にできることがあるかもしれません。他社とコラボして行政に提案することも可能でしょう。
横連携はひとりでは進められません。巻き込める人をどこで見つけるかが重要です。真剣に考える人たちが集まれば案はいろいろ出てくるでしょうが、課題を解決しようとする人や事業者を見つけるのは難しい。
たとえば、単独事業として自治体に見積書を出すと、そのアイデアだけが盗まれて、もっと安い価格で同業他社が落札するといったことが起こりえます。そうならないためには、他社を巻き込んで自社を通さなくては成り立たない企画を考える。駒ケ根市における弊社にとっての他社がJICAであり、JOCAなのです。
――渡邉さんは「生涯活躍のまち」アドバイザー研修※を受講されました。同研修はこれまで試行的事業として行ってきましたが、今後きちんと制度化するには何が必要だと思いますか。
※内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局主催の「生涯活躍のまち」アドバイザー研修。「生涯活躍のまち」の機能(交流・居場所、活躍・しごと、住まい、健康、人の流れ)を理解し、「生涯活躍のまち」事業を進める自治体や事業者に対し、自らの知見を活かしたアドバイスができる人材の育成を目的にしている。
自分の会社に「アドバイザー」という存在を認知させないといけません。アドバイザーとして活動する意味、その必要性を理解させ、会社として取り組むようにさせる。弊社の場合、アドバイザーになっているのは私だけです。実際これが将来どのようなビジネスにつながるか予想が立ちません。会社からは「そんなことにお金を使っている場合じゃない」といわれる可能性もあります。そうならないためにも、たとえば内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局から、アドバイザーの制度は「こういう意図で活用する」「そのためにはこういう人材が必要だ」といったアナウンスをしてもらい、企業のトップや会社全体の信用を得ることが必要だと思います。
アドバイザーとして活動すると、自己の視野は広がります。報酬もある。つまりお金をもらって研修をするという解釈もできるので、「お金を払うのでなく、お金をもらって行う社員研修」となれば、会社も認めてくれるでしょう。現在、どの企業も社員研修をしたくてもできない状態です。アドバイザーの活動をすれば、その人の価値は必ず上がりますし、企業にとって絶対プラスになる。まずは企業側の関心を高めることが重要です。
一方、自治体の立場からすれば、「どの企業とコラボレーションしたいか」「〇〇な商品を売っている企業とどんなことができるのか」といった関心が生まれるかもしれません。旅行会社に対してであれば、ツアーなど誘客できるものを提案してくれるだろうといった期待もあるでしょう。
ツアーについては協業する企業が2~3社加わると、1社では考えられないような企画ができます。私がいいと思うのは人材育成です。地元の課題を解決する高校生向けのプログラムがあったら、地産地消にもつながる。地元を出て行った若者たちが帰ってくるかもしれません。ある私学の理事長が、沖縄県出身のインターン生を4年間受けいれたら、必ず地元に戻るようにするというような、地元の企業に貢献するものをやりたいと話されていました。
もう一度、繰り返せば、①アドバイザーの活動を所属している企業に承認をさせる、②アドバイザーとして地域に赴く人たちが高い意識をもって研修に臨めるようにする。そして、それを継続していく。そうすることで「逆参勤交代」の意味も企業経営者にわかってもらえるのではないでしょうか。
――「Go to トラベル」から緊急事態宣言へと乱高下が続く旅行業界ですが、新型コロナウイルスの収束後の展望は?
収束すれば元に戻ると思っている人が大半だと思いますが、ウイルスは20回を超えて変異するといわれています。強力なワクチンができても、それを超えるウイルスがまたでてくるでしょう。旅行の需要はないのが現状であり、横連携も含めて新規事業で何をするか。非旅行分野を念頭に社内には事業共創推進本部が立ち上げられました。
ウイズコロナにしろ、ポストコロナにしろ、ニューノーマルで生きていくしかない。弊社では、営業マン全員がSDGsの講演をできるようにしようと考えています。まずは社員の意識を高めるためのSDGsのバッジ試験。簡単な基礎知識の試験を受けさせて、その結果から、部署長がバッジをつけていい人とそうでない人とを判断する。コロナ禍と並走しながらでもアドバイスができる営業マン、講演ができる営業マンを育てるしかありません。
現在はビジネスが国内に限られていますが、再び海外展開をするための事前学習につながるようなSDGsを軸にした提案をもっと考える。SDGsチームも営業本部内に立ち上がったので、これまで自分がやっていたことを全部そのチームがすることになりました。今までは自分が課題をつきつけられる側でしたが、今は課題をつきつける立場。私は学校の先生方の課題を吸い上げて、現場に投げる役割を担っています。
国や自治体の発言次第でパッケージツアーの需要も大きく変動します。現在は「Go Toトラベル」もストップするなど、国内旅行は安定的収益にはなりません。安定的なものといったら教育です。私が所属する中部営業本部では事業の7割が教育旅行で占められています。教育は学校だけでなく企業の社員育成もある。そこにわれわれがどこまで立ち入ることができるか。
「生涯活躍のまち」アドバイザーになった皆さんと意見交換し、輪が広がっていけば、いろいろな知恵が生まれ、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局にもいろいろな提案ができるでしょう。企業にも認知されると思います。
ある意味コンサルティングに近い。営業マンがコンサルタントと同じくらい知識や提案力をもち、お客様の課題を解決するアドバイザーとして位置付けられれば、まだまだやれることはたくさんあるはずです。
(聞き手 芳地隆之)

※縄文時代から日本に分布するイネ科の植物。血流の浄化作用、抗酸化作用、整腸の効果などがあるとされる。
――佐久市に地域おこし協力隊として移住するきっかけは何だったのですか。
東日本大震災です。東京生まれ東京育ちである私は当時、コンビニやスーパーなどから商品がなくなり、お金があるのに必要なものが買えないことを初めて体験しました。そのとき思ったのが、「お金の価値って何だろう?」「最終的にはただの紙切れじゃないの?」。それからお金に縛られて人生の選択をするのはおかしいと考え始めました。
――そこから地方移住へとつながっていったのですか。
当時のパートナーが病気だったこともあり、食べものにも気をつけるようになった際、そこから派生して循環型社会に関心をもち、そういう社会を体現してみたいと地方移住に目が向いていったのです。その後、パートナーが亡くなり、「これからは社会に貢献したい」という思いも強くなりました。
――どうして佐久市を選ばれたのですか。
東京に住んでいたころ、八ヶ岳に行った際、日頃の疲れがよくとれて、たまっていたストレスが解消されました。「八ヶ岳は身体に合うんだ」と感じ、移住先は八ヶ岳の近く、山梨か長野かなと考え、(NPO認定法人)ふるさと回帰支援センターに資料を集めに行ったところ、長野県の担当者がすごく親切で。
また、佐久に知り合いが住んでいるのを思い出して、佐久とその近くの上田と小諸を案内してもらいました。
そのなかで佐久は駅前が一番華やか。国道には大型チェーン店が建っているし、東京からは新幹線も通っているので近い。何かあればすぐ東京に帰れる。加えて、晴天率が高いこと、寒いけれども積雪は少ないこともよかった。
ただ、仕事が見つかっていませんでした。そこで、ふるさと回帰支援センターで開催された移住セミナーで佐久市の紹介をされた栁田(清二)市長に「佐久市へ移住したいのだけれども、仕事が見つかっていない」とお話したところ、市長はとても気さくな方で「地域おこし協力隊に応募してみたら」と。地域おこし協力隊の仕組みは知っており、これまでよりも収入がかなり減ることに不安はあったものの、任務はとても興味のあるものだったので応募することにしました。

――どのような任務ですか。
佐久総合病院※がある臼田地区で健康と食をテーマにした活動をするというものです。私は、地域の課題を洗い出し、よりよいまちづくりを進める「うすだまちづくりラボ」の事務局を務め、臼田健康活動サポートセンター(うすだ健康館)という地域の方々の交流の場になっているところで、長野県の伝統食である漬物と多世代交流を掛け合わせたイベントや、漬物の品評会などを開催しました。品評会では高齢者の方に自慢の漬物を1品出してもらい、どれが一番おいしいかを選考したり、漬物の作り方をその場で教えてもらったり。また、地域の方に余った自家栽培の野菜をうすだ健康館まで持ってきてもらい、それをサラダバーにして地域の人に食べてもらうといった交流などを行いました。
健康づくりに関する知見をシェアするため、地域の方に「薬に頼らない体づくり」の年間講座の講師になってもらったり、カイロプラティックと鍼灸という西洋と東洋の自然療法の講師にクロストークをしてもらったりしたこともあります。臼田地区には佐久総合病院のOB、OGの方がたくさんおられるので、地域で健康に暮らすことへの意識は高いと思います。
※農民に健康のための予防を啓蒙し、地域医療の先駆者であった若月俊一医師が長年院長を務めた。
――臼田地区という比較的しっかりとしたコミュニティができているところでも、高齢者、とくに男性の孤立が問題になっていると聞きました。
佐久総合病院を目当てに移住してきた高齢男性が苦労していると聞いています。周りに友人はいないし、地域で独居高齢者の見守りをしている民生委員さんも移住者の情報をもっていないのでアプローチがかけにくく、なかなか地域に出てこられないのです。地元の男性でも、妻が入院した、あるいは要介護の状況になったことで、ご自身が突然鬱になるケースがあるそうです。
日頃から横とのつながりをもっておかないと、いざというときに大変なことになる可能性は誰にでもあると思います。
――加藤さんは地域おこし協力隊を終了した後、合同会社TEAM3939を設立し、共同代表に就任されました。現在、地域おこし協力隊時代から取り組んでおられるマコモという健康食材の事業化を進めておられるとお聞きしています。とても精力的に動かれていますが、コロナ禍によって佐久市での暮らしは変わりましたか。
リモートワークが増えたせいか、東京から人が流れてきているという印象があります。佐久市内にもコワーキングスペースができており、首都圏から佐久市に生活拠点を移したというフリーランスの人と知り合いになりました。
新型コロナウイルスの感染拡大が収束しても、それ以前の生活にそのままは戻らないのではないでしょうか。私はいい方に変わっていくと思います。(コロナ禍以前は)デジタル格差がそのまま情報格差につながる面がありましたが、デジタル化してなかった層がデジタル化に動くと、働き方に関する考え方も大きく変わると思うのです。
リモートワークが浸透すれば多くの人たちは首都圏に住む必要がなくなり、東京一極集中も改善される。通勤に長い時間をかけず、暮らし方のバリエーションも増え、より人本来の生き方に近づいていくのではないでしょうか。感染が拡大し、多くの方が亡くなっている、あるいは苦しんでいる現状には、もちろん心を痛めています。一方で、これから世の中がポジティブに変わることへの期待もあります。
――加藤さんはまさに新しい働き方を実践されているわけですが、その助走期間であった地域おこし協力隊の制度についてどう思われますか。
行政に地域おこし協力隊を育成、マネジメントする能力、あるいはそのための時間が欠けているのではないかと思う時があります。行政と地域おこし協力隊の間に中間支援組織があって、両者の橋渡しができればいいのでしょうが、自分で仕事をつくる、自分から動くという人でなければ、そもそも地域おこし協力隊になるべきではないと私は思います。募集する際「地域おこし協力隊とは何か」という根本の説明をきちんとするべきでしょう。逆に、自分でやりたいことがある人にはぴったりの制度だと思います。3年間あれば人脈がつくれるし、それを自分のビジネスにつなげられますから。
私は就任当初、自分で起業する気はさらさらなかったのですが、任務を遂行していくうちに、「これが自分のビジネスになったら楽しいだろうな」と思うようになりました。そして、任期中の3年間で知り合った皆さんに助けてもらいました。
東京で会社勤めをしていたころに比べると、暮らしの充実度はとても高いと感じています。これも地域おこし協力隊を経たから得られたものです。いきなり個人で地域に入っていたら、とてもできなかったでしょう。だからこそ、この制度がもっと有効に活用されてほしいと思います。
(聞き手:芳地隆之)
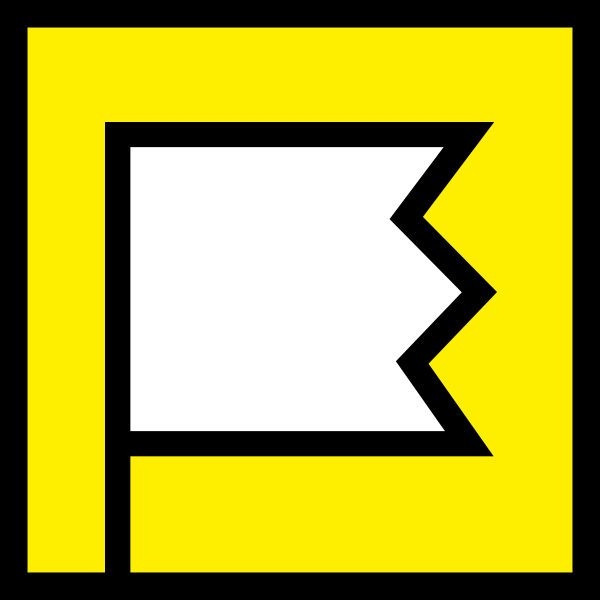




_page-0001.jpg)
.jpg)