Voice
高知県民はみんな高知大生〜知の総和を地域全体で高める〜 高知大学学長 受田浩之さん

うけだ・ひろゆき 1960年北九州市生まれ。九州大学(農学博士)。1991年4月高知大学農学部助教授、2004年12月同教授。2006年4月副学長(地域連携)、2018年4月副学長(地域連携・広報担当)兼務。2015年2月政府の日本版CCRC構想有識者会議委員、同年4月地域協働学部教授、2019年4月理事(地域・国際・広報・IR担当)。四国健康支援食品制度推進委員会委員、高知県まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会委員長、内閣府「地方創生カレッジ推進会議」委員等、多数の要職を務めた後、2024年4月に高知大学学長に就任。
聞き手/松田 智生(生涯活躍のまち推進協議会理事)
構 成/芳地 隆之(生涯活躍のまち推進協議会事務局長)
地方創生以前から始まっていた大学連携
松田 今日は、生涯活躍のまち推進協議会の設立発起人でもある受田先生に、地方創生の取り組みの10年を振り返るとともに、今後を展望してもらいたいと思います。
受田 2015年が地方創生元年といわれていますが、地方創生と大学の関わりは1998年の大学等技術移転促進法(TLO法)の制定にまで遡ります。2000年には総合科学技術会議が設置され、地域再生人材創出拠点の形成のために文部科学省科学技術振興調整費という大型の予算が盛り込まれました。2002年には地域貢献特別支援事業の開始、2003年には地域再生本部の設置。なかでも地域貢献特別支援事業は、文部科学省が国立大学に対して、自治体と協定を結び、自治体の事業をサポートすれば、交付金を付与するというもので、大学は地域にどのような貢献ができるのかを初めて考えるようになりました。
松田 2015年より前に地方創生の胎動があったのですね。
受田 2003年からは自治体で「地域再生計画」が策定されることになりました。自治体が自ら企画、立案していくことに国の予算をつける。その後の「内閣官房まち・ひと・しごと創生本部」による地方創生推進交付金や地方創生加速化交付金の原型といえるでしょう。
松田 2013年には地(知)の拠点整備事業が始まりました。大学が地域の拠点=COC(Center of Community)になるという点で画期的でした。
受田 同年に立ち上げたKICS(高知大学インサイドコミュニティシステム)は、高知県内の34市町村に大学教員をUBC(University Block Coordinator)として配置し、いわば「地域の御用聞き」として課題を掘り起こし、その解決に当たっていくというものです。
日本版CCRCへの逆風~主語は誰か?
松田 当時の日本版CCRC有識者会議には様々な分野の専門家が集まりました。国が主導したことが大きかったと思います。
受田 それ以前に松田さんとともに行った米国のCCRCの視察は、大学が地方創生にどのような貢献ができるかを考えるいい機会だったと思います。学びは生涯にわたって価値を生み出していく。大学が従来のように18歳の若者を集めるだけではなく、アクティブシニアの居場所になるという新たなビジネスモデルの視点をもらいました。
松田 一方で課題もありました。米国のCCRCには高齢者の生きがいづくりや大学のOB・OGへのサポートという役割がありましたが、増田リポートでいわれた「介護難民」という言葉によって、日本では都会の高齢者を地方に移住させる、地方を姥捨て山にするという批判を受けました。
受田 自分たちの主体性がなく、押し付けられたという感じだったのでしょう。地元にいる方々の福利厚生や生きがいづくりなど、環境の改善を同時にやらなければ、特別に優遇された移住者が定着するはずもありません。
松田 主語は「移住者」ではなく、「地元の市民」ということですね。高齢化・少子化のなかで、大学にとっての課題は何だと思われますか。
受田 国立大学に限っていうと、脆弱な財務基盤をどうするか。外部資金を獲得し、自立せよというのが国の方針であり、国立大学が国立大学法人になった意味もそこにあるといわれて20年。各大学は努力をしてきましたが、経営状況が一気に改善する打出の小槌はありません。
解決策のひとつとして出されたのが授業料の値上げです。今年の3月に中央教育審議会(中教審)特別部会で、慶応義塾大学の伊藤公平塾長が「授業料を150万円程度に引き上げるべき」との資料を提出し議論を呼びました。私は6月の国立大学協会の総会で「地方の国立大学からみて、授業料を上げるという方向性はありえない」と発言しました。
人口減少という「静かなる有事」のなかで、日本の力を維持・発展させていくための鍵は、中教審も提言する、「知の総和」をいかに高めていくかにあります。それは量×質で表されますが、量(人口)が減少するのであれば、質(知)を増やすしかない。そこで考えた具体策が、より多くの国民が修士号、博士号を取得するということです。
高知県民は修士、博士をとる
受田 現在、日本の大学進学率は50%強まで上昇している一方、学部から修士課程に進む学生は先進国のなかでも極端に少ない。博士課程に進む学生はなおさらです。OECDにおける100万人あたりの博士号取得者の割合で日本は明らかに劣後しています。国は「博士をとろう」というキャンペーンを展開し、100万人あたりの博士号取得者の数を2040年までに対2020年比で3倍にするという目標を立てています。「とろう」がなぜ「ひらがな」かというと、「本人が博士号を取る」と「企業が博士号取得者を採る」の2つの意味をかけているからです。高知県民も「博士をとろう」という意識が高まり、県民が皆、博士号取得者になるという夢を抱いています。
松田 私も地方創生の根幹は教育だと思っており、いま「第二義務教育制度」を提唱しています。第一の義務教育は6歳から15歳ですが、第二義務教育制度は、15歳から高齢者まで、生涯のなかでもう一度学校で学ぶことを義務とする。人口が減少し、高齢化が進む日本では、人材の高付加価値化が必須であり、経済的な理由で大学に行けなかった人が、大学に通う。社会人はスキルを高めるために、修士や博士を取得する。歴史・文学・一般教養は、歳を重ねてからの方が面白い。高齢者は、地域の小中学校に行けば給食があるので、独居老人は助かりますし、引き込もりの防止や社会参加を促します。体育の時間で介護予防運動を行えば、医療介護費の削減が期待できるでしょう。
そして社会人が子どもたちのIT教育の先生になる、高齢者がまちの歴史の先生になれば、多世代で学び・教え合う「半学半教」のコミュニティになります。つまり、学びを核とした「生涯活躍のまち」です。
日本では少子化で廃校が続々と増えています。図書館や体育施設の稼働率も高くありません。そこに第二義務教育で多世代が入学して、地域の課題を学ぶ。どうして「義務」にするかというと、はじめはあまり乗り気でなかった受動的参加者が義務によって背中を押されると、「よい方向に化ける」。学びや社会参加に積極的になるんですね。
第二義務教育では制度設計が重要で、たとえば50時間学んだら、5万円の地域通貨になったり、50時間が将来の介護サービスの時間に適用できるというような経済的・心理的なインセンティブです。一方で第二義務教育をしなかったら、住民税や固定資産税が高くなるようなペナルティを設けると、渋々参加する。その渋々参加者が人材としての宝の山になる。
受田 OECDにおけるストレートドクター(修士課程から博士課程へ直接進む)の割合と労働生産性の比率を示すデータを見ると、正の相関関係があるといわれています。これをひとつの根拠として、高知県の現状をみると、一番の問題は賃金が安く、県民所得が少ないこと。対東京比で30%減、対全国平均比で15%減という現状から、全要素生産性※1、そして労働生産性※2を高めるにはどうしたらいいか。大学で修士号、博士号を取得した者を、研究開発を含めたイノベーションを誘発する人材として集積し、新結合※3を生みだす。地方の大学の担う役割はそこにあると思います。
※1 Total Factor Productivity=TFP。 GDP 成長を生み出す要因のひとつで、資本や労働といった量的な生産要素の増加以外の質的な成長要因のこと。※2 1人当たりのGDPを人口当たりの労働者数で割った値。※3 経済学者のヨーゼフ・シュンペーターが提唱したイノベーションの概念。これまで組み合わせたことのない要素を組み合わせることによって新たな価値を創造すること。
高知の智恵を活かす
受田 高知は「高い知」と書きますが、かつては「知」が「智恵」の「智」だったそうです。“KOCHI”のKは“Knowledge”、O は独自の文化や歴史が育まれている“Originality”、C は“Creativity”、そこにHの“Humanity”が掛け合わされて、最後にIの“Innovation”にたどり着く。高知市内にある四国霊場第三十一番札所に定められた五台山竹林寺は、四国八十八ヶ所のうち、唯一、文殊菩薩をご本尊にしたお寺です。智恵はそこから授けられたと言い伝えられています。高知が地方創生でやるべきは智恵、知識を基に発展していくことだと歴史が教えてくれているのです。
芳地 先生はご著書『新時代LX 持続可能な地域の未来を切り拓く』で、高知大学の学生と教職員は約7,000人で、高知県の人口の100分の1であるから、関係者1人が県民100人に働きかけをすることで、「高知県民がみんな高知大生」になると書かれています。いまのお話はその発展形なのでしょうか。
受田 現在の高知県の人口は約67万6,000人、高知大学の学生、教職員などを合わせると約7,300人と「93人に1人」が高知大学の関係者になっています。2022年の人口区分では20~24歳が2万8,264人。高知大学では1学年で約1,000人いますから、学生の数が4,500人だとすると、「若者の6.3人に1人」は高知大生ということなる。2040年の予測ではそれが――現在の高知大学の規模が維持されるという前提で――「4人に1人」になる。高知大学がなくなってはだめだということです。
松田 高知大学の卒業生の県内での就職率はどのくらいですか。
受田 現在、高知大学の卒業生のうち7割は県外に出てしまっています。高知県の企業が研究開発志向の修士号、博士号の取得者にとって魅力のある職場になれば、東京へ行く必要はありません。大学進学率を上げるためのEBPM※4 的な視点からいうと、文科省が住民税非課税世帯の子息への学費の助成を始めたことで、同世帯の子息の進学率が40%から70%に上がりました。国立大学協会の総会で、「大学進学のすそ野を広げていくことは、知の総和を高めるエビデンスとして有効ではないのか」と文科省の関係者に述べたところ、「そうです」との回答があり、「だからこそ授業料を上げるのではなく、国が人に投資をするべき」と申し上げました。
イノベーションなくして国の成長なし。東京大学のように研究者の数も研究のための予算もあるわけではない、地方の大学は自らのシーズ=研究の伸びしろがどこにあるかを認識する必要があります。たとえば高知は海に面しているからこそ、海洋に係る研究でトップに立つための企画・立案ができる。高知大学が有する海洋コア国際研究所に全国から生徒たちを集めることで、地域のベンチャー企業を育てる担い手が輩出されるかもしれません。
※4 Evidence Based Policy Making。政策の企画や決定、実行、効果検証を合理的根拠やデータに基づいて行うこと。
大学は地方創生のプラットフォームへ
松田 社会人のなかにも、自分がこれまで取り組んできた仕事を体系化したいと思っている方が少なくありません。私が教鞭をとっている立教セカンドステージ大学や丸の内プラチナ大学の講座の一部を、高知大学で受講するといった大学間の相互乗り入れも有効ではないでしょうか。
受田 人口が減っていくなかで、地方の大学は研究者を維持できるのかという問題に直面するはずです。ひとつの大学がフルセットで担うのではなく、首都圏の大学の一部が高知県に移転するというように、自分たちだけが生き残るという狭隘な考えから脱しなければなりません。
松田 昨年、須崎総合高校を訪れる機会がありました。総合的な探求の時間で、同校の生徒はジビエのレシピを考え、地元の商店街で「ジビンバ丼」を売るといったアイデアを出し、商店街の人も刺激を受けて、がんばろうと気運が盛り上がっていました。高校生が実践しているのは、「企業活動の研究開発×マーケティング×営業×SDGs」そのもの。しかし、当人たちは学校で学んでいることと将来の職業をむすびつけて考えられない現状も知りました。
受田 地方では親、あるいはその上の世代の大学進学率が低いために、家庭内で高等教育の価値が理解されにくい傾向があります。大学卒業した親が増えると、進学率が上がるということが、経年調査で明らかになっていますが、今後は親からのトリクルダウンに期待するよりも、若い世代が親世代に刺激を与えるよう仕向けるべきではないか。現在、高知大学が主導するJST研究プロジェクトの一環として進めている、四万十市に海藻関係の研究所を設立するプロジェクトは、対象を小中学校の生徒まで広げます。同研究に関心をもつことで、将来、大学で学んでもらうという狙いがあるのです。
松田 最後に、もっとよくなる地方創生、もっとよくなる高知という点からメッセージをお願いします。
受田 ここ数年、地方創生の目指す方向が見えづらくなっていましたが、一方で多様なセクターの集まる地域連携プラットフォームを担う大学の役割は明確になってきたように思います。われわれは自らやるべきことを打ち立て、イノベーションの拠点になっていく所存です。
-1024x768.jpg)
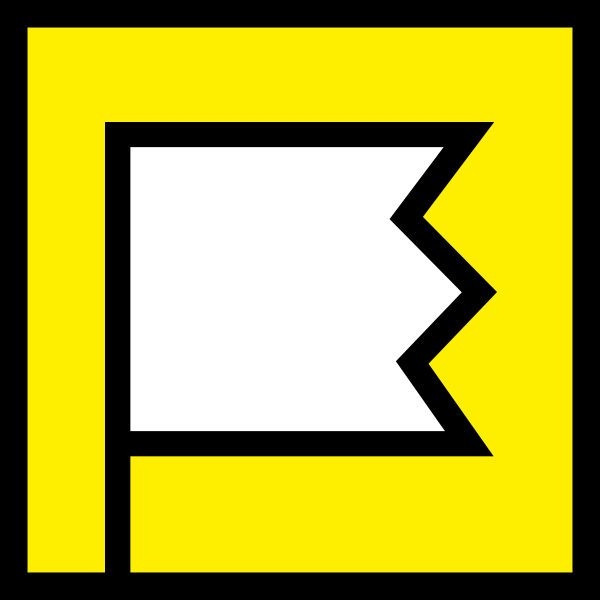





_page-0001.jpg)