News
今月のおススメ本は、小暮太一著『すごい言語化 「伝わる言葉」が一瞬でみつかる方法』ダイヤモンド社
.jpg)
人間は、自分の脳の3%、自分の筋肉の20~30%しか使っていないという。ハーバード大学のジェラルド・ハルトマン教授によれば、人間の意識の95%は言語化されていないそうだ。意識のほとんどは「なんとなくそう思う」レベルに留まっている。
「なんとなくそう思う」を明確な言葉にすること。そのための基本的な考えと技術を伝授するのが本書の目的だ。相手の関心を引くキャッチコピーではない。言語化と聞くと、私たちはいかに(how)伝えるかに腐心しがちだが、何を(What)を伝えるかが曖昧な限り、Howをいくら磨いても意味がない。たとえば、スターバックスは、自宅でも、仕事場でもない、自分の第三の居場所=サードプレイスを提供しますという。「おしゃれなカフェ」ではなく、「サードプレイス」という言葉を使うことで、スターバックスが提供したい空間とその価値を言語化したのである。
言葉が世の中を動かすこともある。現在のようなインバウンドの増加は、「観光資源」という言語化なしには不可能だっただろう。いまもむかしも日本の地理や自然環境は変わっていないわけで、外国人観光客に迎え入れる私たちが、この言葉によって、自分たちの地域のもつ魅力に目を向けたのである。
著者は言語化するための「PIDA の4法則」を挙げる。P:Purpose(言語化する目的は何か)、I:Item(相手に伝えるべき項目は何か)、D:Define(その項目を定義する)、A:Apply(伝わる表現に当てはめる)。自社の高価格商品を買ってもらうために(P)、品質の高さや他の商品との差別化のポイントを伝え(I)、その商品の故障率が低いこと、信頼できる会社がつくっていること、顧客が抱えている他社商品への不満を解消するといったことを明確にし(D)、それを伝えるために、故障率は年間0.001%である、従来の商品に見られた〇〇のマイナスポイントを解消しているというように具体的に表現をする(A)。さらには伝えるべき項目として、提供する価値の言語化、他社との差別化の言語化、自社の信頼性の言語化、価値が提供される理屈の言語化、相手に取ってもらいたい行動の言語化の5段階に分ける。
これらはビジネスに必須のスキルとして記されているが、自身の潜在能力を引き出すそれとしても読めるのではないか。あなたが「自分らしく生きたい」と思うとする。しかしあなたのいう「自分らしく」の自分の意識のうち95%は言語化されていない。つまり、あなたの知る自分はほんの5%程度であり、残りの95%を言語化しようという試みが、あなたを自分という未知の領域に連れていってくれるのである。(芳地隆之)




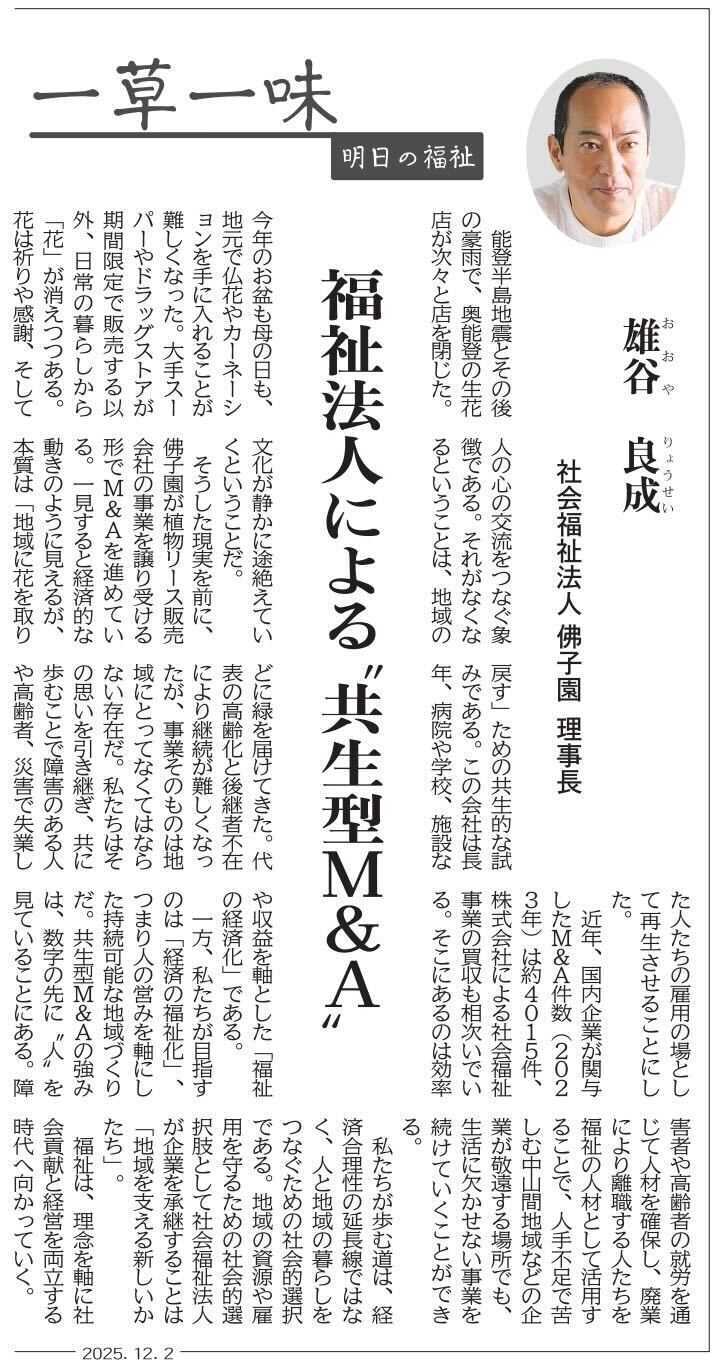

_page-0001.jpg)