Voice
みんなで取り組み、みんなで目指す、地方創生2.0〜伊東良孝担当大臣に聞く〜
-scaled.jpg)
先般、伊東大臣に、地方創生について、これまでの10年間を振り返り、どのような点にメリットがあったか、一方で残された課題に向けての改善点、国として地方創生2.0が目指すものは何かについてお話しいただきました。そして、これまで各地で頑張ってきた自治体や事業者、ならびに地方創生2.0に関心を有する自治体や事業者へのメッセージをお伝えくださいました。
伊東 良孝(いとう よしたか)内閣府特命担当大臣(地方創生)新しい地方経済・生活環境創生担当 北海道出身。北海道教育大学卒業。釧路市議会議員(3期)、北海道議会議員(2期)、釧路市長(2期)を経て、2009年衆議院議員初当選、現在6期目。財務大臣政務官、農林水産副大臣を歴任し、24年10月から現職。
聞き手/松田 智生( 生涯活躍のまち推進協議会理事、三菱総合研究所主席研究員)
構 成/芳地 隆之(生涯活躍のまち推進協議会事務局長)
松田 伊東大臣は、これまでの地方創生10年間を振り返り、どのような点にメリットがあったとお考えでしょうか。
伊東大臣 石破総理が初代の地方創生担当大臣として、地方創生に取り組まれて以降、地方創生版の3本の矢である交付金などの財政支援、人材派遣などの人材支援、RESAS※1などの情報支援を活用し、各地
で地域の活性化につながる様々な好事例が全国で生み出されました。たとえば、地方創生の交付金を用いて、ドローンを活用した買い物支援サービスや、私も2024年12月に訪問した茨城県境町で行われてい
る、自動運転バスを活用した地域交通などが挙げられます。同町では「子育て支援日本一」を目指した移住定住施策として、PFI事業※2により子育て応援住宅を整備し、子育て世帯等の家賃の減額や、戸建て住宅に25年居住した方に土地と住宅を無償譲渡する予定、など新たな取組もみられます。
「生涯活躍のまち」の展開については、2024年10月時点で取組を推進している、または推進意向がある自治体は421団体となっているなど、着実に進んできているものと考えています。
※1 地域経済分析システム「RESAS(リーサス)」。地域経済に関する官民の様々なデータを分かりやすく「見える化」することで、各地域で産業構造や人口動態等の現状や課題を容易に把握・分析できるようにすることを目的としたシステム。
※2 民間資金等活用事業(Private Finance Initiative)。公共施設の設計・建設・維持管理・運営などを、民間の資金やノウハウを活用して行う事業手法。公共サービスの効率化やコスト削減、民間企業の事業機会創出などを目指して行われる。
松田 一方で残された課題もあるかと思います。今後に向けて改善すべき点をお聞かせください。
伊東大臣 これまでの地方創生の取組の結果として、人口減少や東京圏への一極集中の流れを変えるまでには至っていないと受け止めています。2025年6月には、今後10年間を見据えた地方創生2.0の方向性を提示する「地方創生2.0基本構想」を閣議決定しました。ここでは、地方創生1.0の反省すべき点についても記載しております。具体的には4点、①人口減少を受け止めた上の対応の不足、②若者や女性が地域から流出する要因へのリーチの不足、③国と地方の役割の検討の不足、関係機関等の連携の不足、④地域の多様なステークホルダーが一体となった取組の不足が反省点として挙げられます。地方創生2.0については、こういったこれまでの成果と反省を踏まえ、地方の意見も伺いながら、進めていく必要があると考えています。
-1024x756.jpg)
松田 上記と関連し、国として地方創生2. 0が目指すものは何かについてお話しいただければ幸いです。
伊東大臣 基本構想でお示ししている、地方創生2.0の「目指す姿」は、「強い経済」と「豊かな生活環境」の基盤に支えられる「新しい日本・楽しい日本」を創ることです。そして、上述の地方創生1.0の反省を踏まえ、①少子化対策には引き続き取り組むものの、当面は人口減少するという事態を正面から受け止め、適応策を講じる、②若者や女性にも選ばれる地方が重要との考え方を強く打ち出す、③様々な要素の掛け合わせ、いわゆる「新結合」により新たな価値を創出するなど、地方に仕事をつくるのみならず、「稼げる地方」をつくる、④急速かつ飛躍的に発展するAIを始めとしたデジタル技術を徹底活用する、⑤「ふるさと住民登録制度」を創設し、関係人口を活かした都市と地方の支え合い、人材の好循環を創出する、などの新たな考え方のもと、地方創生2.0を進めていく必要があると考えています。
全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0については、2025年3月に長野県伊那市における地方創生の有識者会議に出席させていただくなかで、長野県宮田村の「オヒサマの森」のお話を伺いました。ここでは、小規模であっても、高齢者、障害者、こどもなど、年齢や障害の有無にかかわらず、様々な方が居場所と役割をもてる施設を運営されており、こうした取組を全国に広げていきたいと感じたところです。
こうしたことも踏まえ、基本構想では、「小規模であっても年齢や障害の有無を問わず様々な人々が集い、それぞれが持つ能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らすことができる場(小規模・地域共生ホーム型CCRC)の整備を進める」こととしており、当面の目標として、「3年後に、全国で100か所小規模・地域共生ホーム型CCRCの展開を目指す」ことも盛り込んでおります。引き続き、全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の推進に向けて取り組んでまいります。
松田 これまで各地で頑張ってきた自治体や事業者、ならびに地方創生2.0に関心を有する自治体や事業者へのメッセージをお願いします。
伊東大臣 地方創生に御尽力いただいているみなさまに心から敬意を表します。地方創生2.0は、国とともに、地域の住民の方々や産官学金労言士などの地域のみなさまが一体となって実現を目指すものであり、「みんなで取り組むもの」、「みんなで実現を目指す社会像」であると考えています。今般決定した基本構想を踏まえ、地方創生2.0を「令和の日本列島改造」として力強く進めてまいります。
地方創生の実現のためには、地方の思いを大切にし、関係者の声に耳を傾け、国・地方・国民が一緒になって取り組む必要があります。令和7年度当初予算において倍増した新地方創生交付金なども活用し、自治体の自主性と創意工夫に基づく取組を強力に後押ししていきたいと考えています。引き続き、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。




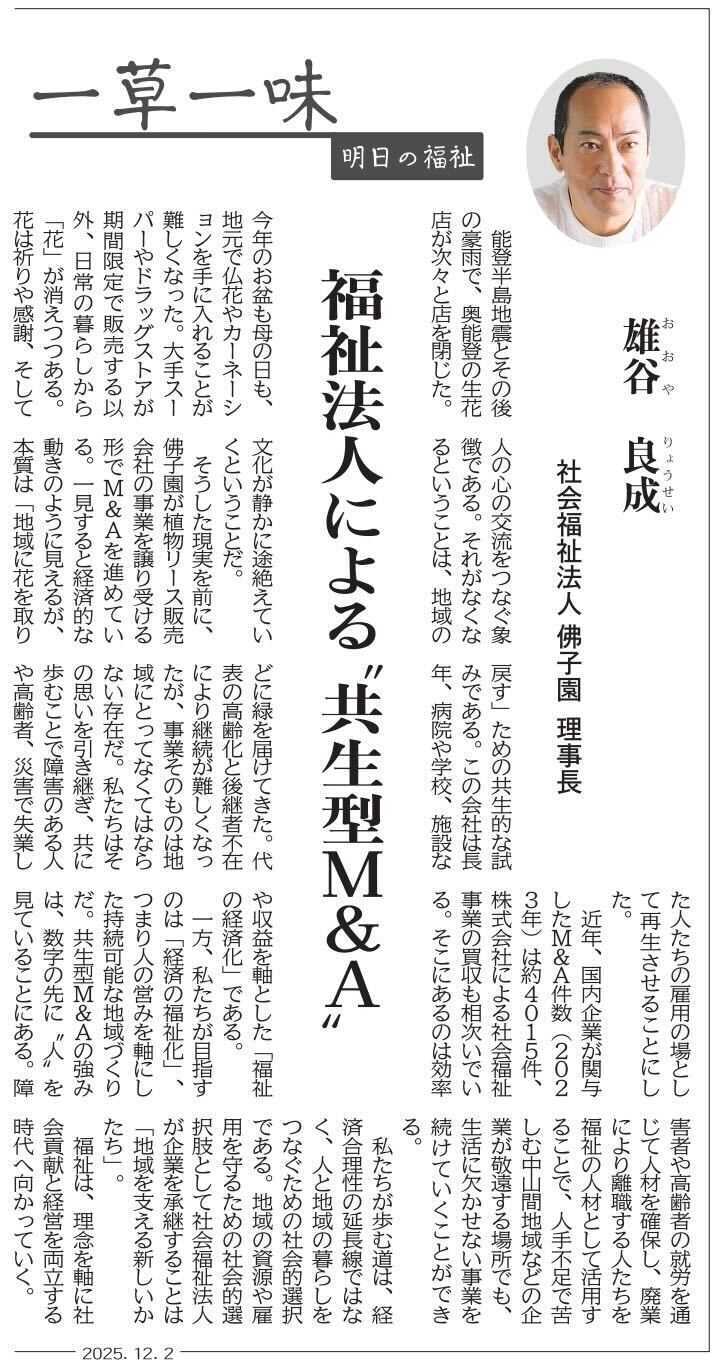

_page-0001.jpg)