Blog
作り手と受け手の関係を越えて~あーすぷらざでのごちゃまぜ映画会~

(上映後のアフタートーク。左から東志津監督、伊勢真一監督)
8月9日、横浜市本郷台の「あーすぷらざ」5F映像ホールで「ごちゃまぜ映画会」が開催されました。今年度の第2回目となる本イベントでは、戦後80年を迎えたのを機に、東志津監督の『美しいひと』(2013年)、伊勢真一監督『いまはむかし』(2021年)が上映されました。
午前中に上映された『美しいひと』は東監督が、1945年8月に広島、長崎で被爆した方々に向き合ったドキュメンタリーです。最初に登場するのは、韓国の陜川(ハプチョン)原爆被害者社福祉会館で余生を送る人々。ひとりの女性は幼いころ両親とともに韓国から広島へ渡り、7歳で被爆しました。それ以前に身体に障害を負っていた彼女は、カメラの前で辛い、死にたいとつぶやきます。続いて監督はオランダへ飛びます。長崎の爆心地近くにあった捕虜収容所に収容されていたオランダ人被爆者を訪ねるためです。ひとりは原爆投下を「明確に人を殺しにきた」といいました。そして日本へ。16歳の時に長崎で被爆した龍(りゅう)智江子さん。原爆で母と弟を、後遺症で父を亡くしました。戦後もしばらく被曝を隠して生きてきたことなどを龍さんは息子とともに振り返ります。

語られるのは原爆投下の時の話だけではありません。被爆当時よりも、自分がその後、どうやって生きてきたのか。上記とは別のオランダ人男性の被爆者は、すでに90歳を超えていて、当時の記憶が少し交ざってしまうのですが、東監督はあえてその姿も映します。その理由を同監督は、上映後の伊勢監督とのアフタートークでこう語りました。
「毎年8月のこの時期になると、戦争を振り返る特集が組まれます。なかでも原爆投下後の広島、長崎がいかに凄惨だったかという話になりますが、私はこの映画で被爆者の人生をトータルで見たかった。被爆後もーー死者の記憶とともにーー生き抜いてきた方々は、原爆を落とした側よりも強いんだということを伝えたかったからです」
伊勢監督は、東監督の作り方がとても丁寧だと評して、こう言います。
「戦争は悲惨であり、あってはならないものだけれども、だからといって声高に反戦を叫ぶのではなく、目の前の人と向き合って、心の奥から紡ぎ出される言葉を拾っていく。それによって見る人が人間の尊さを感じられれば、それを踏みにじる戦争に対する嫌悪の気持ちも生まれる。反戦よりも厭戦の感覚を抱かせる映画は強いんじゃないかな」
午後の上映となった『いまはむかし 父・ジャワ・幻のフィルム』は伊勢監督が、父親である伊勢長之助さんが戦中にインドネシアで日本の国策映画をつくっていた足跡を追った作品です。伊勢長之助監督は戦後、東京裁判のドキュメンタリーをはじめ、1960年代まで様々な分野の記録映画を製作しました。

「インドネシアのスタジオでは日本人とインドネシア人のスタッフがほぼ対等で仕事をしていたようです。とはいえ、父が映画を通して日本の侵略に加担していたことは否めません。ただ、彼の映画は単なるプロパガンダではなく、インドネシア人の労働を称えるものもありました。もしぼくが父の立場だったら、同じように一生懸命、映画をつくったんじゃないかと思う。だから一方的に批判する作品にはできなかった。ぼくのなかに当事者意識があるからだと思います」
伊勢監督は、戦後、映画監督の伊丹万作(故・伊丹十三の父)が「国民だって戦時中は女性のパーマネントはけしからんとか、ゲートルの巻き方がなってないとか、お互いを監視し、戦争を支持してきた。それなのに、戦争に負けた後は、あれは軍部が悪かったと責任をかぶせてしまった」ことを痛烈に批判したことを話しました。
伊勢監督は「ごちゃまぜ映画会」についてこんなことも語っています。
「ぼくの作品のカメラマンを務めていた故・瀬川順一さんは、ひとつの映画には3つの作品があると言っていました。まずは自分が撮ったすべてのフィルム、次に監督が編集して完成させたフィルム、そしてそれを観客の前で上映したフィルム。映画は生き物です。古い作品でも、いまを生きる人が見ることによって息を吹き返すこともある。今日の『美しいひと』もそうでしょう。アフタートークで、見てくださった方の質問や意見を聞くと、こんな風に解釈してくれているんだ、といった作り手が意識していなかった新しい発見があります。映画は最終的には作り手と受け手の共同作業で完成するのだと思います」
だから、ごちゃまぜ映画会。
現在、NHKで放映中の三浦しをん原作の連続ドラマ『舟を編む~私、辞書をつくります~』は、若い女性編集者が、専門家や上司、同僚らとともに辞書を編纂する物語です。タイトルの「舟」は豊饒な言葉の海を進むための羅針盤(=辞書)を指しています。劇中、辞書の役割は、知らない言葉の意味を調べて終わりではなく、人が言葉の世界の入り口に立てるようにすることだというセリフがあります。
これに倣えば、ごちゃまぜ映画会は、映画を上映して終わりなのではなく、上映を通して仲間が生まれる。だから始まり。伊勢監督が、どうして自主上映スタイルを続けているのか、その理由が体感できる映画会でした。
今年度のごちゃまぜ映画会は、第3回は12月、第4回は来年の3月を予定しています。(芳地隆之)





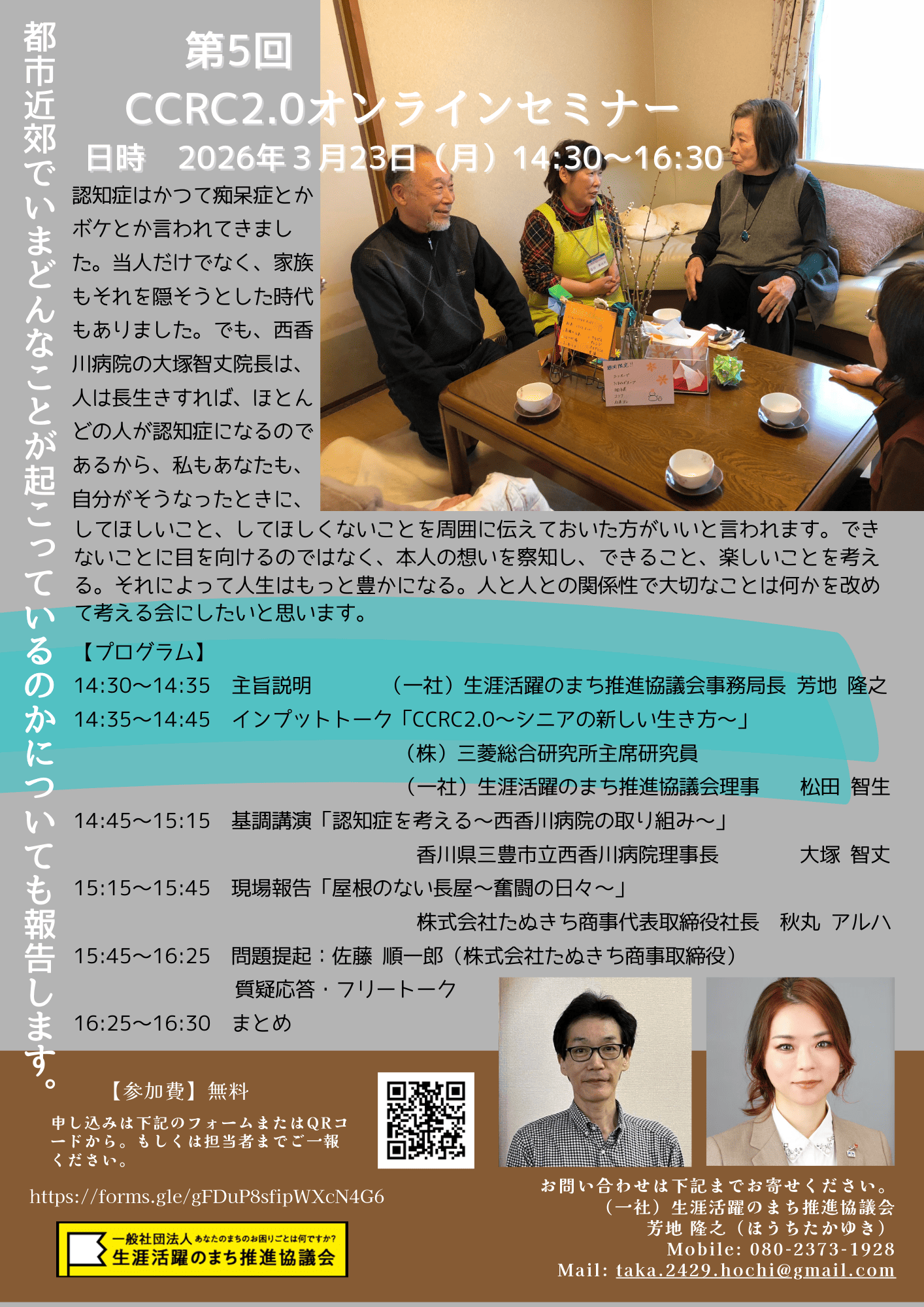

_page-0001.jpg)