Blog
マジックワード「ARIGATO」~佛子園・JOCA海外研修 in スペイン

9月21日(日)~10月2日(木)にかけて、社会福祉法人佛子園と公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)合同の海外研修が行われました。今年の行き先はスペインのバルセロナとグラナダでした。
佛子園が1996年から実施している海外研修は、2010年の法人設立50周年を機に、「人が生きる意味」や「幸福とは何か」というテーマを掲げ、雄谷良成・佛子園理事長/JOCA会長はじめ両団体の理事による審査員チームがプログラムを入念に設計します。参加者はチームに分かれて挑戦。行く先の国に関わるペーパーテスト、脳トレ的なゲーム、クイズと運動、スポーツ競技、笑いなど、その場、その場で提示される多種多様な課題に四苦八苦し、知力・体力が試され、学びが深まるという仕掛けになっています。


クイズに答えながらウォーキング。カタルーニャ美術館の立つ丘の上まで何度も往復。地元の人たちが不思議そうな目で見ていました(笑)。
なかでもメインとなるのは、研修のテーマを深掘りするため、グループごとに行うフィールドワークです。テーマは「可処分時間」。スペイン人に「あなたが1人で過ごす時間をどう使ったら、家族や友人、仲間との関係がもっと良くなると思いますか?」を尋ねて、課題①「可処分時間の達人」を探し、課題②スマホやSNSなどをどのように使っているかを聞き、それらを踏まえて、課題③「可処分時間活用法についての提案」をする。各グループは①~③に取り組むべく、どこへ行って、どんな人たちに会いにいくのかを発表します(下記のような感じです)。
可処分時間とは何か、可処分時間の使い方がその人にどのような影響を与えるかについては、本HPの下記のブログをご一読ください。
時間がないってホント?~北陸地区知的障害者福祉協会・雄谷良成会長の講義~
各チームは9月25日午前にバルセロナで散会し、27日夕方にグラナダのホテルで集合。翌日にはフィールドワークの結果のプレゼンテーションを行います。上記のグループは、バルセロナで見たメルセ祭(バルセロナの守護神メルセの日を祝う、バルセロナ最大の祭り。9月24日には「人間の塔」がサン・ジャウマ広場で披露され、ヒガンテス〔巨大人形〕が町を練り歩く)で人間の塔を披露したグラシア地区のグループを取材し、生きがいを持ち、自分の時間を地域や社会への貢献のためにも使い、文化や伝統を継承する地区のメンバーを可処分時間の達人に選び、プレゼンテーションで1位に輝きました。

グループで一番小さな子どもがてっぺんまで上がります。

フィールドワークしていると、多くの方々が私たちが着ているTシャツを見て、「Oh, ARIGATO !」と声をかけてくれます。それをきっかけに話が弾み、交流を深めることができました。驚いたのは日本のアニメに詳しいだけでなくテーマソングまで歌えた人、アニメキャラクターによるゲームプログラムをつくっている人、さらには山形県で「マタギ」をテーマにしたドキュメンタリーを撮影したという人などに出会えたことです。

私たちが言葉の違う国に行くとき、最初に知りたいと思うのは「ありがとう」ではないでしょうか。スペイン語を知らない私たちもまずは「Gracias(グラシアス)」、そして「Hola(オラ=「やあ」や「こんにちは」という意味のカジュアルな挨拶)」を覚えました。
ありがとう=感謝の意味を深く考えるようになったのは、私たちが2024年1月に発生した能登半島地震の支援活動を通してでした。雄谷理事長は感謝には3つのステップがあるとして、次のようなことを語っています。
最初は「親切」への感謝。炊き出しや倒壊家屋の整理など支援をしてくれたことへの「ありがとう」です。その次は「日常」への感謝。水や電気が通っていること、ご飯が食べられること、ゆっくり眠る場所があることなど、普段は当たり前だと思っていたことが、どんなに大切なことかがわかる。そして最後は「逆境」への感謝です。災害という厳しい状況が経験や学びになったと思える人が獲得する境地。輪島KABULETの職員の多くが「逆境」への感謝の念を抱くようになりました。
次に「ありがとう」の3ステップです。皆さんが物を落とした時、それを拾ってくれた人に「ありがとう」って言いますよね。「親切」への感謝とも関連しますが、翌日になっても「拾ってくれたこと」への感謝の気持ちは持続していますか。すっかり薄れているか、あるいは忘れているのではないでしょうか。なぜならこの「ありがとう」は拾ってくれたという「行為」に対するもの。つまり承認(recognition)だからです。
皆さんは、部下が用事を済ませてくれたとき、承認で済ませていませんか。仕事だから当たり前だろうなんて思っていませんか。それは本当の「ありがとう」のレベルではありません。管理職が部下に、たとえば「君は家では親御さんの介護もあるのに、よくここまでやってくれたね。ありがとう」という。それは「人」への感謝(appreciation)。本当の「ありがとう」です。
その先のステップもあります。「〇〇は自分の家も壊れているのに、ここに来て、ここまでやってくれている。すごいなあ」と周囲に伝える(affirmation)。これは人から人にとどまらない、組織として「ありがとう」を広げるということです。
この海外研修は、参加者にとって怖い面もあります。面白いプログラムの数々なのですが、時には気持ちが追い込まれたり、体力を消耗したりすることで、イライラしたり、落ち込んだり、投げやりになったり、普段は職場で隠しているものが顔や態度に出てしまいます。それによってチーム内で不協和音が生じることもあります。そういうときにメンバーはどうするか。励ます、労わる、慰めるはもちろんのこと、同じ目標を達成するためには、ときに相手に耳が痛いことでも直言しなければなりません。現地で密なコミュニケーションを交わすことで、チームビルディングの訓練にもなる。海外研修に行く前と後では互いの関係がより深くなっていることに参加者は気づくのです。
海外研修のプログラムは審査員チームによって1年間かけて練り上げられます。参加者の何倍もの労力がかかります。人を育てるために知識や経験を惜しみなく投入する。それに対して参加者はどのように応えるのかも問われます。
帰国直後の羽田空港での解団式で、雄谷理事長は「ARIGATO」のベースとなる共感として、認知的共感、感情的共感、共感的配慮という言葉が挙げました。認知的共感とは相手の反応や気持ちを想像し、理解する力。感情的共感とは相手の感情に寄り添い、自分のことのように悲しんだり、喜んだりする力。そして共感的配慮とは相手が感じている感情を考え理解し、さらに相手に対して気配りすることを意味します。認知的共感、感情的共感を経て、何らかの行動に移す力といえるかもしれません。雄谷理事長は言葉を換えて次のように説明します。
「ありがとう」の最終形態である共感的配慮は口だけでなく「感謝は行動に移してこそ感謝になる」というもので、それには時間的要素が強く反映されます。簡単に言えば、お世話になったらその場で「ありがとう」という気持ちを何とか伝えようとすることです。
気持ちを何とか伝えよう。これは海外研修で常にトライしていたことでもありました。私たちの問いかけに真摯に答えてくれたスペインの方々にどのように感謝を届けるか。日本から用意したお土産を渡す、相手の知りたい日本のことを説明する、そもそも、なぜ私たちが「可処分時間」についてインタビューしているかをわかってもらうよう言葉を尽くす(拙い語彙でしたが)。
そうした行為の大切さも身をもって学んだ私たち参加者は帰国後、各々の職場に戻っていきました。






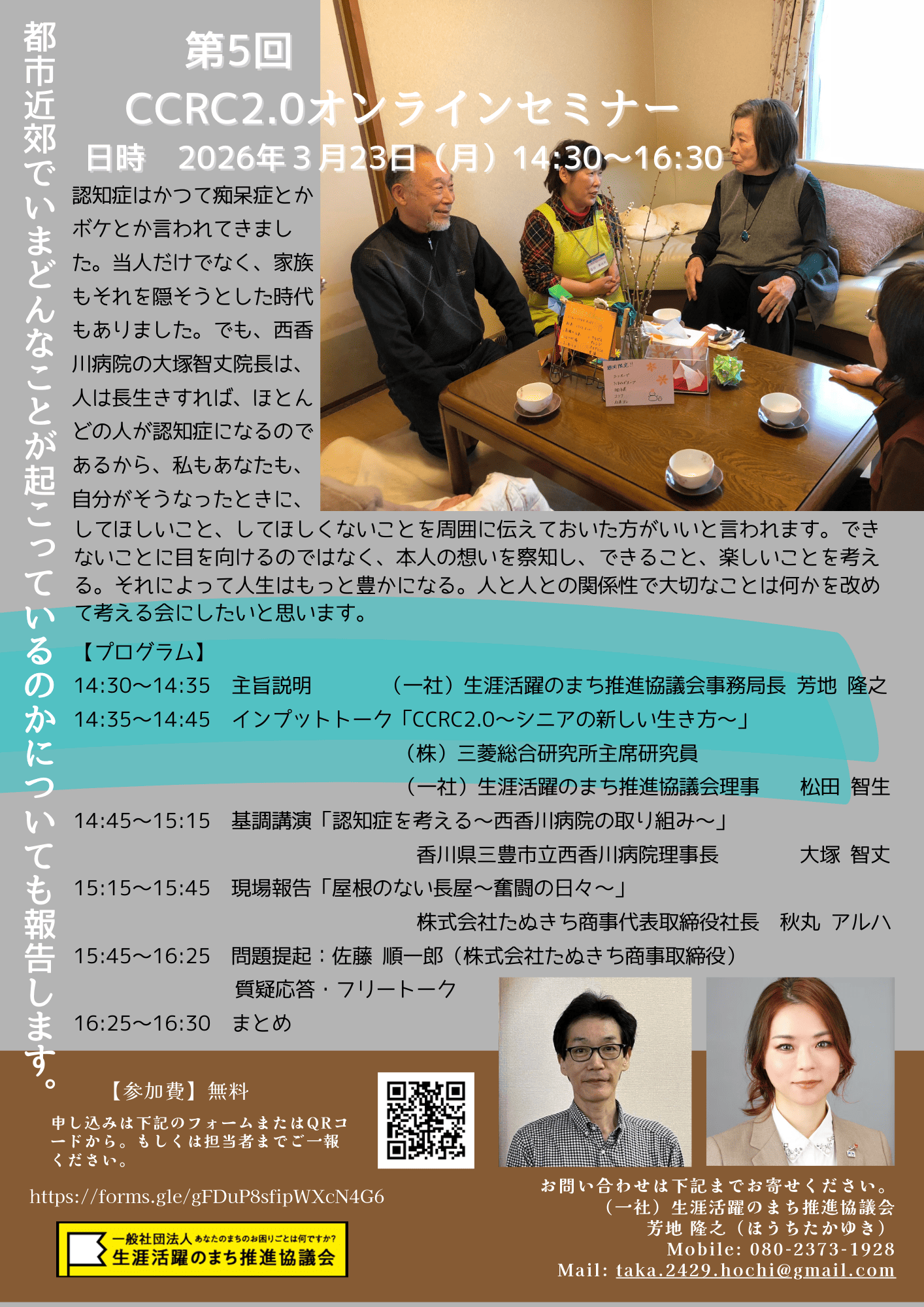

_page-0001.jpg)