Blog
演劇とまちづくりの似ているところ

昨日、一都四県、大阪府、兵庫県、福岡県を対象とする非常事態宣言がなされました。 すでに密閉・密集・密接の「三密」が生じる場として、劇場への出入りは自粛の対象になっており、知人のいる劇団でも残念ながら公演を中止せざるをえない状況に追い込まれています。一刻でも早い新型コロナの終息を願うばかりです。
演劇とまちづくりは親和性が高いことは多くの方々がおっしゃるところです。少なからぬ演劇人が実践されています。
新国立劇場演劇部門芸術監督を務め、紫綬褒章も受賞された著名な演出家でる栗山民也さんは、 自書『演出家の仕事』(岩波新書)でこんなことを書いておられます。
「演劇に限らず、今の時代に、一番大事なことは、『聞くこと』のように思えてなりません」
演出家にとって重要なのは「何を見て、何を聞くのか」だと栗山さんは説きます。それは演出家のみならず、俳優にも当てはまる。自分が話すよりに、相手の言葉に耳を傾けること。それによって自分のなかに起こる化学反応を、彼や彼女は言葉と身体で表現する。それが演技なのだというのです。 ひとつの言葉がもうひとつの言葉を生む。それはつねに美しいメロディを奏でるとは限りません。神経を逆撫でするような不協和音も発するでしょう。それら交錯するイメージを膨らませては壊し、その上に新しい解釈を積み重ねていく作業に完全はありません。それは初日の幕が開いても終わることなく、観客の反応も取り込みながら楽日まで続きます。
同じ地域に住む人々が、自分たちのまちをどうするかで、ああだ、こうだと話し合いながら、小さな計画を実行し、途中で間違いに気づいて改善を重ねながら、よりよい構想へのバージョンアップしていく。そんな地域づくりの過程に似ているのでないでしょうか。
そうした演劇活動を地方で行う動きとしては、1976年に早稲田小劇場の演出家であった鈴木忠志さんが富山県西部の利賀村に拠点を移し、1980年代に日本で初めての世界演劇祭「利賀フェスティバル」を開催したことが思い出されます。 1994年に施設は富山県に移管され、富山県立の利賀芸術公園となって以降は、劇場、稽古場、宿舎などが整備。現在は周辺の「利賀大山房」「リフトシアター」なども合せて7つの劇場、稽古場、200名以上が宿泊できる宿舎などを擁する舞台芸術の一大拠点となっています。
近年では平田オリザさんが主宰する劇団青年団が拠点を兵庫県豊岡市に移しました。平田さんはその理由として、土地の利便性やまちのもつポテンシャルなどを挙げています。土地の値段は東京の10分の1程度。アクセスもよく、新しくできる劇場はJR荏原駅から徒歩1分、最寄りのインターから車で5分、コウノトリ但馬空港から車で10分。渋滞もなければ、駐車場にもお金もかかりません。城崎温泉が多くの外国人観光客を呼び寄せており、それに夏の海水浴やシーカヤック、冬のスキーというスポーツの魅力と、演劇というアートが加われば、魅力的なリゾート地になるというのです。
平田さんは数多くの本を記しておられますが、そのなかのひとつ『下り坂をそろそろと下りる』(講談社現代新書)で、「街中に、映画館もジャズ喫茶もライブハウスも古本屋もなくし、のっぺりとしたつまらない街、男女の出会いのない街を創っておいて、行政が慣れない婚活パーティーなどやっている。本末転倒ではないか」と書いています。また、未婚率の高さと関連して、男女が偶然に出会える場がどんどん少なくなっている日本のまち、とりわけ人口減少に悩む地方で一番欠けているのは「艶」=「文化」ではないか、とも。平田さんはまた、文化度を測る目安のひとつとして、「お母さんが昼間、子どもを保育園に預けて芝居を見に行っても、後ろ指さされない世の中」を挙げています。そこはたぶん、いまより居心地のいいところになるでしょう。
青年団には岡山県奈義町に移住した菅原直樹さんという俳優・介護福祉士の方がいます。菅原さんは、ご自身のおばあさんが認知症になったときのことをこう語っています。
「ぼくが中学生の頃、家に2つあったコロッケを食べちゃった後、おばあちゃんに『あれ一個あげようと思ったのに』と言われたんです。そこでぼくが『誰に?』って聞いたら、後ろを指さして『タンスの人』と答えたんです。普通は『そんなわけないでしょ』と反応するのでしょうが、ぼくは面白いと思ったんですよね」
高齢者介護の現場と演劇の相性がいいという菅原さんは、いまでは全国各地で高齢者や介護者と一緒に演劇公演や、認知症ケアに演劇的手法を取り入れたワークショップを行っています(上記の写真はワークショップのチラシです)。
新型コロナが蔓延し、劇場に足を運ぶのが難しくなっているいまだからこそ、あえて考えたいテーマです。
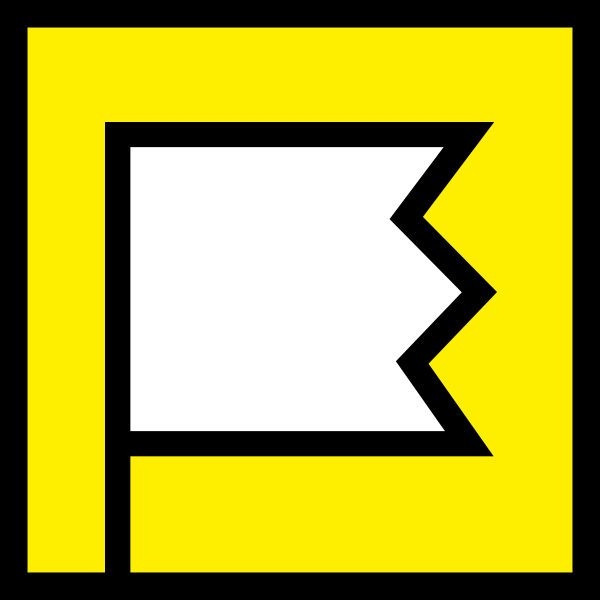



_page-0001.jpg)
.jpg)
