Voice
これまでを描くことで、これからが見えてくる~ドキュメンタリー映画監督・伊勢真一さんに聞く~

9月に封切りされた伊勢真一監督のドキュメンタリー『大好き』は、障害のある姪の西村奈緒さんと母親の信子さんとの50年を振り返る作品です。奈緒さんは生後間もなく、難治性のてんかんと知的障害のあることがわかり、医者から「この子は長く生きられません」といわれました。伊勢監督は「奈緒ちゃん」が生きていたことを記録に残しておこうと撮影を開始。その後、てんかんの専門病院での持続的な治療と薬の効果があり、なによりお母さんが「地域で育てる」という方針をもっていたことで、「奈緒ちゃん」が明るく元気に育っていきました。その姿を描いたのが『奈緒ちゃん』(1995年)です。その後、信子さんと仲間たちがハンディキャップをもつ人々やその家族を支える地域作業所を立ち上げるまでを描いた『ぴぐれっと』(2002年)、撮影を始めて25年目の節目につくった『ありがとう~奈緒ちゃん自立への25年~』(2007年)、さらにそれから10年を経た家族を撮った『やさしくなあに~奈緒ちゃんと家族の35年~』(2017年)を発表。今回は『奈緒ちゃん』シリーズの5作目になります。そこで伊勢監督に、ひとつの家族を撮り続けること、それを伝えることの意味をお聞きしました。
――新作『大好き』のキャッチコピーは「50年に及ぶ大好きの記憶」とあります。「記録」ではないのですか。
記録というと、時系列に「こうやって生きてきました」と整理する作業に近くなってしまいます。一方、記憶はあっちこっちに飛ぶじゃないですか。子どものころのことを思い出した後に、一昨日の出来事が頭に浮かんだりとか。過去が無意識のうちに脚色されることもある。そうしたことも含んだものがパーソナル・ヒストリーであって、それをAIが「それはあなたの記憶違いで〇〇年の出来事です」と修正して年譜にしてしまうと、人間の記憶する力がどんどん弱くなるなってしまう。だからこのドキュメンタリーは記録ではなく、記憶なんです。
『大好き』を見てくれた何人かの方々から「子どもを産むか、産まないかと迷っていたんだけれども、この映画を観て、産もうと決心しました」という感想をいただきました。もし自分の子どもに障害があっても――もちろんなくても――奈緒ちゃんのお母さんみたいに「私がこの子に育てられた」と言えると思った、自分もそういうお母さんになりたいとアンケートに書かかれているんですね。ぼくは奈緒ちゃんとお母さんの50年間を追ってきたんだけれども、観る人はこの映画を通して自分の50年先を見ている。過去を伝えることは未来を想像させる力にもなるんだと思いました。
――これは作り手の意図しないことであり、作品が監督の手から離れてひとり歩きを始めた感じですね。
映画より感想の方が素晴らしいんですよ。これまでの『奈緒ちゃん』シリーズでも「登場する人たちが素敵ですね」と言われるけれど、撮る側の方はあまり褒めてくれない(笑)。いわゆる作家主義的なつくり方をしないからでしょうか。ある程度、経験を積むと、「こうしたらお客さんに受けるだろうな」とか、「評論家の評価が高くなるにはこうすればいいかも」といったものがわかってきます。やろうと思えばできるんだけれども、自分が観客の立場になると、そうした作り手の意図が見えてしまって、「つまんないなあ」と思う。
――伊勢監督が以前、「“こういうアングルがいいんじゃないか”とか“この場面でこんなことを言ってくれると面白くなるんじゃないか”と考えているうちはだめで、被写体が醸し出す“私を映して”を受けてカメラを回すようになった時、自分は初めてプロになったと思った」と言っておられたことを思い出します。
2年前の「ごちゃまぜ映画会」で雄谷さん(社会福祉法人佛子園理事長、公益社団法人青年海外協力協会会長、当協議会会長を務める雄谷良成)と対談したときですね。その際は雄谷さんを追ったNHKのドキュメンタリー(「こころの時代 宗教と人生 “ごちゃまぜ”で生きていく」)の話にもなり、番組で取り上げられた宮沢賢治の詩「雨ニモマケズ」が印象的でした。この詩の最後にある「ミンナニデクノボウトヨバレ ホメラレモセズ クニモサレズ サウイフモノニ ワタシハ ナリタイ」の「褒められもせず 苦にもされず」っていう生き方はとても高度だと思います。賢治も「そういう人に私はなりたい」、まだ「デクノボウ」にはなれていないと言っていますよね。
――伊勢監督はその場に溶け込むので被写体は撮られていることを意識しない。いわば「苦にされない」存在なのではないでしょうか。
雄谷さんは、「雨ニモマケズ」のメモとして賢治が手帳に記した「行ッテ」が赤字で書かれていることに注目していましたよね。ぼくにはドキュメンタリーの企画の段階でどういう作品にするというゴールはあっても、構成やストーリーをきちんと組み立ててから動くというより、とりあえず「行って」、そこで会った人やその場の空気を映像にしていくという手法をとっています。
その過程で奈緒ちゃんがもっている人間のベースのようなものが見えてきました。人を思いやる心や争いごとをやめさせようとする姿勢です。人間はそもそもそういうものをもって生まれてくるのに、大きくなるにつれ、社会や人間関係にもまれて、知識や知恵が増えていくことで失ってしまう。ところが奈緒ちゃんには、いまもそれがある。だから周りをやさしい気持ちにしてくれる。お母さんがノートに書いた「奈緒さんは、人間社会の中に、現れて、苦しみを背負いながら、身をもって、お母さん、お父さん、記くん、お友達、職員さん、おばさんたち……そして社会の人達に“何が大切”なのかを教えて来てくれた」ことなんだと思います。
――今回は人に伝えることの大切さをあらためて実感したそうですね。
『奈緒ちゃん』シリーズのようなパーソナル・ヒストリーだけでなく、戦争でも、災害でも、そう。今年のノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会(被団協)は、自分たちの体験を語り継ぎ、二度と核兵器が使われないことを訴えてきた活動が評価されました。いま佛子園や青年海外協力協会の皆さんが能登半島で取り組んでいる災害支援活動を伝えていくことも未来につながっていきます。それをマスメディアを通してではなく、当事者の言葉として語ることが大切です。
ぼくが自主上映という形式にこだわっているのも、映画に描かれる当事者の言葉を観客という、もうひとりの当事者に直接手渡したいから。映画が完成し、観客が鑑賞して終わりではない、人から人へと伝わっていくプロセスを大切にする。先達たちが行ってきた、作り手主導の映画運動とは違うムーブメントにしたいんです。
ぼくは昨年と今年、癌の手術をしました。自分の死が近づいていると自覚し、残された時間で自分は何を伝えることができるのかを問うています。ぼくは自分の作品をヒューマン・ドキュメンタリーだと思っているのですが、他の映画監督からは「“ヒューマン“なんて甘い」と言われることがあります。「こころ温まる」とか「感動的な」というフレーズをイメージさせるのでしょう、「現実はそんなきれいごとじゃない」と。しかし、ヒューマンの語源はフムス(humus)というラテン語で、地面とか腐食土を意味します。人間はこの地上の被造物であるということでヒューマニティ (humanity)と呼ばれるそうで、きれいごとではなく、むしろカオスに近い。人間って正直で優しいところもあれば、嘘をついたり、ずるかったりもするわけじゃないですか。綺麗な面も汚い面も、それら全部をひっくるめて「ヒューマン」だとすれば、ぼくはこれからもヒューマン・ドキュメンタリーを撮っていきたいと思います。

伊勢監督作品の上映のお申し込みは下記のHPへご連絡ください。
(聞き手 芳地 隆之)
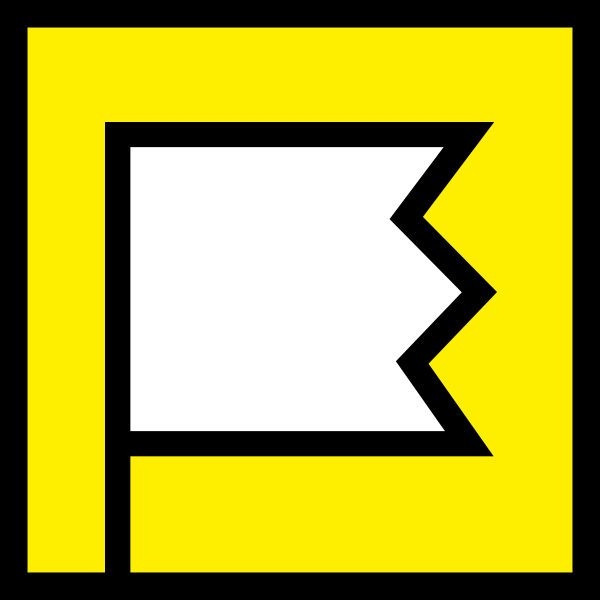





-scaled.jpg)