Blog
地方創生2.0は総力戦で取り組もう
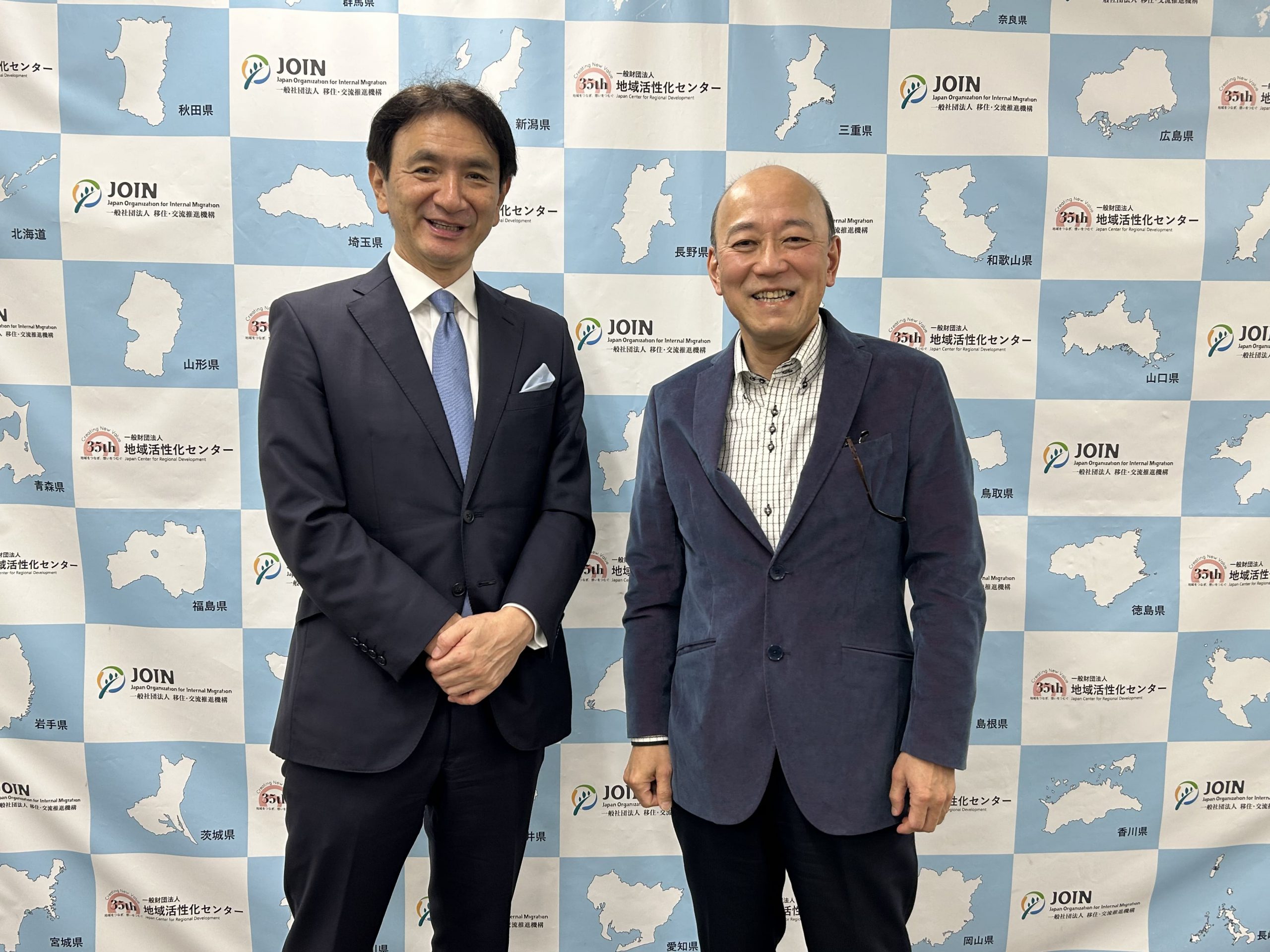
「地方創生から10年」インタビュー⑨
林﨑 理(はやしざき おさむ)さん
一般財団法人地方活性化センター理事長/内閣官房参与(地方創生担当)
1983年東京大学法学部卒業。旧自治省に入省。内閣官房内閣審議官、総務省自治税務局長、自治財政局長、消防庁長官、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部総括官などを歴任。
聞き手/ 松田 智生 (三菱総合研究所主席研究員/生涯活躍のまち推進協議会理事)
構 成/ 芳地 隆之(生涯活躍のまち推進協議会事務局長)
地方創生の機は熟した
松田 日本版CCRC=生涯活躍のスタート時は、「元気な高齢者の地方移住」に注目が集まりました。地方創生2.0と連動してCCRCも新たなステージに入るべきと考えていますが、CCRC2.0の主眼は、多世代が住み、住民のQOLを上げ、雇用を生み、税収を増やすというところにあると思います。たとえば愛媛県の宇和島市では、廃校、廃幼稚園を改修し、地元の方々が集える地域交流拠点を3カ所つくりました。そこで高齢者の介護予防、子どもの放課後教室などを行うほか、健康体操参加のインセンティブとして「健康マイレージ」がもらえるという制度、日本郵便と連携したスマートスピーカーによる見守り、オンライン診療の導入などを続けたところ、この10年間で介護保険の認定率が低下したそうです。宇和島市長の判断で、市役所の担当者を10年間異動させなかったことも成功の要因だと思います。
林崎 「地方創生が始まり10年が経ったにもかかわらず、東京一極集中はむしろ進み、地方の活力という点でも大きな前進はなかった。結局、地方間の首都圏人口の取り合いだった」と否定的にとらえる評論家は少なくありません。しかし、この10年間で各地に成功例が生まれました。これには政策面の充実も寄与したと思います。石破茂・初代地方創生担当大臣時代に始まった1,000億円の地方創生交付金は画期的でした。その特長のひとつが、補助金採択で終わりではなく、当時の内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が自治体からの相談に乗り、「ここはもっとこうしたらどうか」というコンサルティング機能を有していたことです。私自身も同事務局地方創生総括官として、当時交付金の使い勝手をよくするため、各省庁間の連携もサポートしてきました。
従来の地域活性化と一線を画するものとしては、地域経済循環分析を勧めたことも挙げられます。地域のお金がどこに流れているか、電力代は地域の外に出てしまっていないか、コンビニは売上が本社に吸い上げられているのではないか。自分たちで地域を分析して、あれこれ工夫して、観光客を呼んでお金を落としてもらうなど、地域のお金が外に流れていかないように考えるためのものです。
人に関する制度も充実しました。たとえば総務省による地域おこし協力隊や地域活性化企業人※1、そしてプロフェッショナル人材※2などです。プロフェッショナル人材事業では、大手企業のOB・OGと経営の行き詰っている地方企業とのマッチングも行うことで成功例も多く生まれました。
※1) 三大都市圏に所在する民間企業等の社員を地方で受け入れる制度。
※2) 新規事業の立ち上げや新商品の開発、生産性の向上など「攻めの経営」をするために必要な専門的スキルや経験を持つ人。年齢制限や必須の資格はない。
-1024x768.jpg)
そして、この10年間で機は熟したといってもいいでしょう。理由としては次の3点が挙げられます。①地方の置かれた状況の深刻化。以前であれば、Uターンする人に「故郷を捨てたくせに」などという人もいた。「よそ者なんてもってのほか」とみる人もいた。しかし、いまやどこもUターン、よそ者はウェルカム。地方創生を担うのは若者、よそ者、ばか者とはいわれるが、そういう人たちが成功事例を生み出してきている。②テクノロジーの進歩。インターネットはもちろん、最近でいえば生成AI。近い将来にはロボットが席巻するかもしれない。オンライン診療、水や電気という基幹的なインフラの地方分散も可能となった。ドローンもそう。③価値観の変化。頑張って勉強し、いい学校に入って、いい会社で働いて偉くなることよりも、社会的な課題の解決を自分の仕事にしたいという人が出てきた。
魂に火をつける
松田 私は、地方創生における持続性を、社会的な持続性(社会的合意形成)、経済的な持続性(税収の増加)、ウェルビーイング的な持続性(健康寿命の延伸)、人材的な持続性(関係人口の拡大)に分けられると思っていますが、地方創生における課題を挙げるとすると何でしょうか。産官学金労言のうち、「産」でいうと、「地方創生でいくら儲かるのか」という企業の論理があります――それに対して、私は「わが社が地方創生に取り組んでいることが自社の社員の育成につながる」といったSDGsや人的資本経営という非財務価値を強調していますが――。「官」でいうと、中央官庁における縦割りの壁、自治体では首長の交代による政策の変化、担当者の異動による熱の消失、「学」では大学が地域に出ていこうとしないといった現状があるのではないでしょうか。いずれも例外はありますが。
林崎 日本は今年で戦後80年、明治維新からは157年です。この間、西欧社会のキャッチアップを主眼にしてきたことで、日本社会は様々な分野における組織の機能分化、役割分担の細分化とともに、分析も批判的視点から、といった傾向が強くなりました。しかし、地方の過疎地ではそんなことではやっていけない。ひとりで何役もやり、周囲の人々と協力しながら、物事に取り組むのが当たり前です。
たとえば徳島県神山町の取り組み※3は、このままでは自分たちの地域は滅びてしまうという危機感から始まりました。そして、どういう地域であれば人が出ていかず、人がやってくるようになるのか、を徹底的に話し合い、可能性が感じられる地域となるべく、教育、住宅、福祉、産業などをどうするか、ICTインフラを活用した地域づくりに邁進しました。NPO法人グリーンバレー理事長の大南信也さんの始めた事業がみんなの心をひとつにし、「自分たちも何かできるんじゃないか」と思わせるようになったのです。グリーンバレーが注目されるようになった当初、役場は取材を申し込まれても「あれは民間の事業だから」と断っていたようですが、あまりに注目が集まってきたので、とうとう町長が職員をグリーンバレーに張り付けたと聞いています。
※3)外部から若者やクリエイティブな人材を誘致し、ICTインフラ等を活用して、中山間にあっても多様な働き方を実現できるビジネスの場をつくった。
松田 民間の取組に触発されて首長がリーダーシップを発揮し、職員のやる気を生み、それに共感する住民がわがまちのよさを再認識したということですね。
林崎 人の魂に火がついているかがポイントです。これは日々の座学だけでは難しい。私たち地域活性化センターには全国の自治体から50人以上の若手が集まり、それに民間からの出向者も加わって各地の優れた取り組みの調査研究、先進地における地方創生実践塾や地域リーダー養成塾、地方創生フォーラムなどの企画と実施を行っています。学びと仕事を通じて魂に地方創生の火がつくのです。
いい仕組みをつくっても、人を育てなければ、それを活かすことはできません。中央官庁は、補助金などの仕組み、いわゆる施策を考えることはできても「人づくり」にまではなかなかリーチできない。ではどうするか。こここそ都道府県の出番だと思うのです。高知県のように優秀な若手を集落に派遣して、地元と一緒に課題解決に取り組む。現場を知って苦労しながら取り組ませることで自分たちの人材が育ち、ひいては市町村の人材育成の支援につながる。そういった取組が全国の都道府県でも拡がることを期待します。
縦の糸と横の糸を織り込む
松田 地方創生の新しさは市町村が直接国に相談できるようになったことでしたが、人材育成という役割は都道府県が担うのですね。
林崎 自分の県の市町村のなかで、やる気はあっても頑張り切れないところを助けるために、県庁の職員が現場に入って地方創生・地域の活性化にまい進する。それによって、県庁の職員も応援を受けた市町村の職員も大きく育つ。そんな取組を全国の都道府県知事のリーダーシップに期待したいですね。
基礎自治体といっても、十数万人規模の市町村になると、地域を挙げて話し合うことはなかなかできません。でも顔の見える関係ができるとうまくいきやすい。大きな自治体でも地域の商店街の人たちなどが地元を盛り上げる例はありますが、民間だけだとお互いが遠慮しあったりして、とかく動きにくい。そこに役場が入っていって、調整やアドバイスをする=コーディネーターの役割を果たすことが重要です。
松田 まちづくりは人づくり、地方創生は人材育成が鍵ですね。地方創生には民間主導型、行政主導型がありますが、民間同士をつなぐコーディネーターを行政が担うと。
林崎 講演ではときどき中島みゆきの『糸』のフレーズを口ずさむんですよ(笑)。「縦の糸はあなた 横の糸は私」。縦の糸が制度や補助金だとすれば、横の糸は地域。縦の糸がいくらいいものでも、横の糸を織り込まなくては、「織りなす布はいつか誰かを暖めうる」ことができません。私が現役で主に取り組んできたのは「縦の糸」でした。当センターの理事長として多くの現場をみて、横の糸の重要性に改めて気づきました。
地方の経営者のマインドセットを変える
芳地 林崎理事長が総括官を務められた内閣官房まち・ひと・しごと創生本部は、その後、デジタル田園都市国家構想実現会議に名称を変え、現在は新しい地方経済・生活環境創生本部となっています。政府の方向性として変わったところがあるとお考えですか。
林崎 大きくは変わっていません。その時々にスポットライトを当てたということだと思います。「デジタル田園都市」は、観念的には「まち・ひと・しごと創生」や「新しい地方経済・生活環境創生」の一部とみています。究極の目的は地方を活性化させることであり、今回の「地方創生2.0」という看板でわかりやすい姿になったといえるのではないでしょうか。
ニッセイ基礎研究所の天野馨南子さんがこんなことを言っています。地方の人々は進学で街に出る、就職で中核都市に出る、そこから首都圏へ行ってしまうと。福岡県でさえ、九州中から集める人口よりも、東京へ行ってしまう人口の方が多い。その大きな理由は、若い女性の働く場所が少ないことです。結婚をしたいという若い人の割合は80%、ほしい子どもの数も変わっていません。ところが結婚観が変わりました。かつて「働く夫と専業主婦」だったのが、「夫婦共働きの二馬力」が男女ともに当然、となっている。地方では二馬力をやろうにも女性の就職先が限られているので、女性は首都圏に行ってしまう。その結果、首都圏では単身女性が、地方では単身男性が増えている状態になった。中核都市の企業経営者は従来のマインドを変えて、若い女性社員を採用し、戦力として使っていくべきだと天野さんは言っています。
たとえば東京の小さな町工場で、若い女性を採用することで新しいアイデアが生まれ、業績も上がったという事例が出てきています。そうしたことをストーリーとして地方の経営者に伝えることが重要だと思います。また、首都圏の企業は「早期退職」ばかりではなく、「スキルを活かして、第二の人生を地方で送る」という選択肢を示すべきです。現行のシステムでは社員さんもぜんぜん元気が出ないので。
松田 地方創生を振返ると、「ここがよかった・地方創生」、「ここが課題だった・地方創生」がありますが、これからの未来に向けて「もっとよくなる・地方創生」としてメッセージをお願いいたします。
林崎 総力戦です。人口減少、高齢化が進んでいく日本では、目標と価値を共有し、各々が役割をもち、互いに協力し合って、息を合わせながらやっていく。産官学金労言や住民みんなで。それによって力を最大限に発揮でき、楽しく住みよい地域、よりよい日本づくりに繋がると思います。
一橋大学一橋ビジネススクールの楠木健教授が「世界最強の商売人」というジョークを紹介していました。日本人が中国人に「日本人は商売が甘い。やっぱり商売は中国や華僑には到底かなわない」というと、それを聞いた華僑の人は「そうは言うけれども、華僑だってユダヤ商人には負ける、なにせ経験が違うから」と答える。するとユダヤ商人は、「ユダヤ商人も、インドの印僑にはまるでかなわない」といい、印僑の人たちは「それでも唯一われわれがまるで歯が立たない商売人がいる。それはレバシリだ。レバノン、シリアの人たちは、歴史的にも古い商業経済の地で鍛えられてきた人たちなので、彼らこそ世界最強だ」という。そこで、レバシリの人に「あなたたちが世界最強だそうですね」と聞くと、「その通り。しかし、われわれにもたったひとつ、勝てない民族がある。それは束になったときの日本人だ」と返ってくるというオチです。ひとつの方向を向いて結束すれば、日本人は力を発揮できる。今の時代、パイをどう分けるかというゼロサムの議論ばかりになりがちですが、発想を変えて、力を合わせてパイを大きくすることを目指すべきだと思います。






-scaled.jpg)