Blog
能登半島地震から1年 復興のまちづくりを追う第1弾ドキュメンタリー

2024年1月1日の大地震から1年3カ月、同年9月21日から23日にかけての豪雨災害から約6カ月後の輪島市で活動する福祉に携わる方々を描いた作品です。
取材を受けたのは谷内勝次さんと細川貴子さん。お2人とも輪島市内の福祉事業所に勤めていました。そして自宅は被災しました。
自身の勤め先が立ち行かなくなった谷内さんは、社会福祉法人佛子園と公益社団法人青年海外協力協会(JOCA)が共同で運営する輪島KABULET施設長の寺田さんに「うちで働かないか」と誘われて、施設内を見学したときにびっくりしたといいます。
職員も利用者も実ににこやかな表情をしているからです。「2度も被災しているのにどうして?」。その理由を知りたいと思い、輪島KABULETの高齢者デイサービスで働き始めました。
細川さんは、勤務していた特別養護老人ホームの入居者さんが能登半島から避難してしたことから事業を中断せざるをえなくなりました。その後は地域の支援活動への従事を経て、現在はJOCAの職員として仮設住宅の見守り支援活動をボランティアの皆さんとともに行っています。
仮設住宅の見守りだけでは災害関連死を防ぐことはできない。住民の皆さんが一緒に食事やお風呂を楽しみ、自ら主体的に運営できるコミュニティ・センター(コミセン)が必要であるーー発災直後から佛子園とJOCAが訴えていたことです。コミセンの第1号は4月20日、輪島マリンタウンの仮設住宅団地に隣接する場所でオープンします。
「私が楽しく活動していなければ、(仮設住宅の皆さんも)楽しくないと思うので、私も楽しみながらコミセンに関わっていきたい」という細川さん。
「2度も被災しているのに、輪島KABULETの職員や利用者さんはなんでにこやかなんだろう」。輪島KABULETを訪れた際にそう思ったという谷内さんですが、ご自身、そして細川さんも、いまでは笑顔で活動をしています。
それはどうして? 今度はこのドキュメンタリーを見る私たちが考える番。被災者でありながら、支援者でもある。全国社会福祉法人経営者協議会・企画製作による、福祉のもつ秘めた力を感じさせてくれるドキュメンタリー。第2弾も楽しみです。




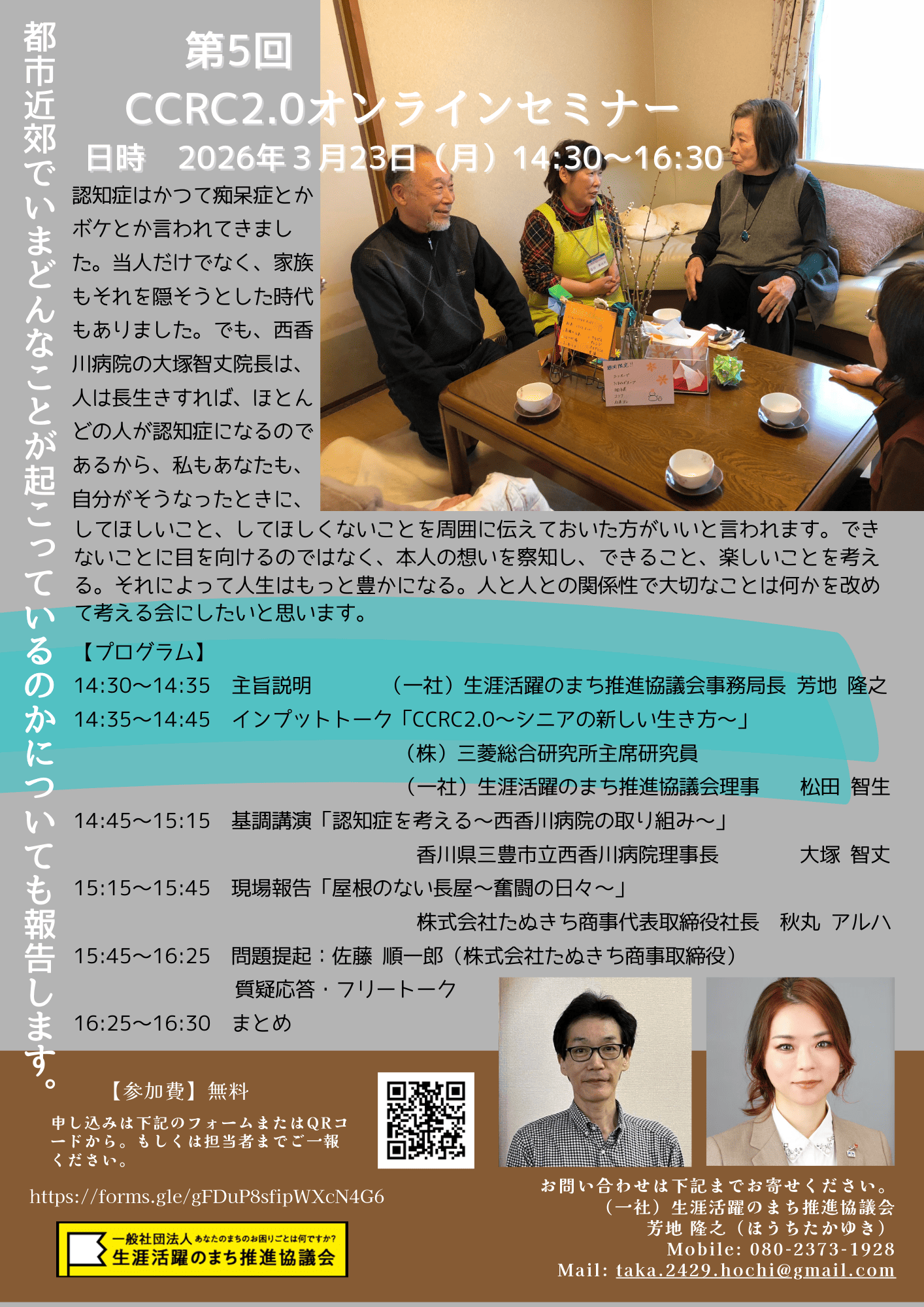

_page-0001.jpg)