News
私主語のCCRC2.0で実現する多世代の幸せ~石破茂総理インタビュ~

6月13日に地方創生2.0基本構想が閣議決定されました。うち「6.政策パッケージ(主な施策)」では、「全世代・全員活躍型「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開」として、「年齢や障害の有無を問わず多様な人々が集い、持つ能力を希望に応じて発揮し、生きがいを持って暮らす小規模・地域共生ホーム型CCRCの推進を中心として、「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0の展開に向け、省庁横断的な「『生涯活躍のまち』(日本版CCRC)2.0検討チーム」を設置し、制度・運用の見直し等を行う」とあります。3年後に、全国で100か所小規模・地域共生ホーム型CCRCの展開を目指すという数値目標も掲げました(「地方創生2.0基本構想」(概要)より)。
今般、公務ご多忙ななか、石破茂内閣総理大臣に時間をとっていただき、「生涯活躍のまち」(日本版CCRC)2.0への総理の思いと国の目指す方向についてお聞きしました。
石破 茂(いしば しげる)内閣総理大臣
1957(昭和32)年生まれ、鳥取県出身。慶應義塾大学法学部卒。1986年衆議院議員に全国最年少で初当選。防衛大臣、農林水産大臣、地方創生・国家戦略特別区域担当大臣などを歴任。2024年10月1日、第102代内閣総理大臣に就任。同年11月には第2次石破内閣が発足。
聞き手/松田 智生( 生涯活躍のまち推進協議会理事、三菱総合研究所主席研究員)
構 成/芳地 隆之(生涯活躍のまち推進協議会事務局長)
松田 石破総理が初代地方創生担当大臣の2015年に、日本版CCRC構想有識者会議が設置され、私も委員として参加しました。私は2010年からCCRCの有望性を、個人のQOL×地域活性化×新産業創造の「三方よし」として提言し続けてきましたが、今回総理が改めてCCRCの再検討を指示された背景やきっかけをお聞かせください。
石破総理 初代地方創生大臣として、ワシントンD.C.の中心部から車で2時間ほどの、廃校になった大学の敷地を活かしたCCRCを視察したときです。そこに住む高齢者が実に楽しそうで、ある方が「これからお迎えが来て、また生まれ変わることがあったとしても、私はもう一度ここに帰ってきて暮らしたい」と言っておられたことに驚きました。入居者だけではありません。スタッフも実に生き生きしている。私は今回CCRC2.0として重点施策と位置づけました。高齢者、大人、若者、子ども、誰もが集えるコミュニティ、高齢者が地域のプレイヤーとして活躍し、生きがいを感じられるような場所をつくりたいと思ったからです。しかしながら、CCRCはわが国でなかなか定着しなかった。米国でできて、なぜ日本でできないのか、という思いを持ち続けていた私は、地方創生2.0においてもう一度CCRCに焦点を当てることにしました。

松田 この10年間でCCRCは「高齢者の地方移住」との先入観や批判を受けることがありましたが、総理の指摘される「多世代が集い、生きがいを持つコミュニティ」を否定する人はいないはずです。そしてこの10年の間に全国で多くの好事例も生まれました。愛媛県宇和島市の廃幼稚園を利活用した地域の多世代交流拠点では、介護予防や放課後教室が行われており、高齢者が子どもに勉強を教える光景が見られます。同市は、青年海外協力隊(JICA海外協力隊)の派遣前訓練を受け入れており、彼らは人口が減少する地域で担い手となり、関係人口の拡大に寄与しています。そして市役所の担当者は、約10年異動せずにこの施策を担いキャリアを積んでいます。これが市長の慧眼で担当者の継続性を保ったことが成功の要因です。
総理はCCRC2.0の実現に向けて、自治体、あるいは事業主体にどのような期待をお持ちですか。
石破総理 地方の中小規模の自治体では人口減少が止まりません。そして若者の雇用の創出や多世代の社会参加による地域活性化が急務であり、政府として積極的に後押ししたい。解決策を見いだせない地方に、国が「こうやったらどうか」と提案し、「一緒にやろう」と併走することが大事だと思います。
そうしたなか各地では特別養護老人ホームをはじめ、高齢者の入所施設の老朽化や空きが生じていることに危機感を抱いた首長が、従来の建物を利活用したCCRCに取り組むことを考え始めています。

松田 私はCCRC2.0を語る際に「主語」は何かが重要だと考えています。たとえば、「特養が老朽化している」という「施設主語」ではなく、「私がいきいき暮らす」、「私が仕事や社会参加でわくわくする」という住民主体の「私主語」が先に来るべきではないかと。CCRC1.0がなかなか定着しなかったのは、「地方が人口減少するので移住しましょう」というロジックだったからではないでしょうか。
石破総理 たとえば、社会福祉法人佛子園が運営するShare金沢、長野県宮田村の介護・商業の複合施設「わが家 オヒサマの森」では、高齢者や子ども、その親御さんなど、多世代が実に楽しそうでした。「楽しい」の主語は「私」になりますね。
芳地 私は(地方創生2.0基本方針の)「新しい日本・楽しい日本」というキャッチフレーズがとてもいいと思います。人口減に対する危機意識をもつことも大切ですが、人を起動させるのは「楽しさ」だということをこの10年間で実感しました。
松田 CCRCはQOL向上が原点であり、それは「生活の質」というよりも「人生の質」だと思います。そして、ワクワク感や楽しいがそのベースにあるのだと思います。
「私」主語は、自分に言い聞かせている言葉です。いま危惧するのが、「国がだめだ」とか「県がよくない」というように、他人主語の風潮であり、主語を他者で語っても物事は前には進みません。自ら主体的に何ができるかを基点にすれば、CCRC2.0も地方創生2.0も、建設的に進むはずです。
石破総理 愛知県長久手市に子どもから高齢者までが交ざって暮らすコミュニティ「ゴジカラ村」を立ち上げた吉田一平氏が、後に長久手市長に転身した際、「わが市役所には『あれ、やってくれ』『これやってくれ』という人ではなく、『あれ、やらせろ』『これ、やらせろ』という人に来てもらいたい」と言っていました。行政に依存するのではなく、住民自らが行動を起こすことが大切です。
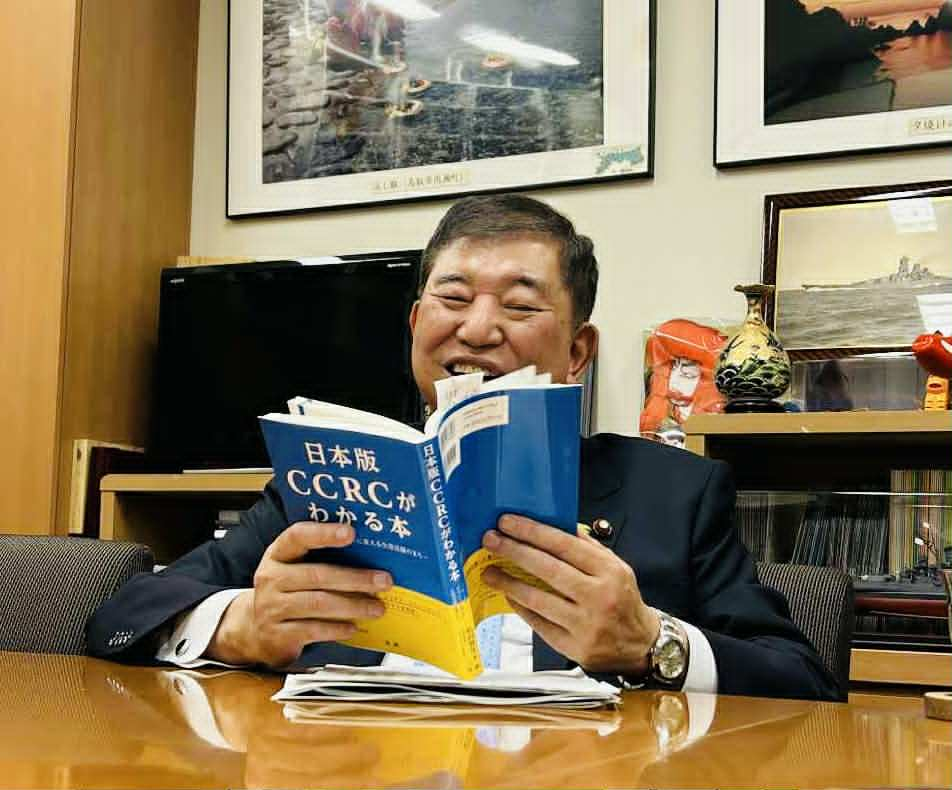
芳地 上述の佛子園、そして公益社団法人青年海外協力協会は能登半島地震・豪雨災害の支援活動を通して、仮設住宅の敷地内にコミュニティ・センターを開設しました。食事、入浴、集会、福祉サービスを提供し、雇用も生む地域住民の拠り所です。地方創生2.0基本方針の「6.政策パッケージ(主な施策)」に記されている「ソフト・ハードを組み合わせた総合的な事前防災を推進する」に相応しい場所だと思います。
石破総理 能登半島における被災地支援と生涯活躍のまちの親和性は高いと思います。能登半島の被災地でこそ、みんなで助け合う、新しい地方創生のモデルが生まれるのではないでしょうか。
こういう幸せの形をCCRC2.0で実現していきたい。2年間の地方創生大臣時代には具現化できなかったものの、その思いを共有してくだった全国の自治体、事業主体、支援団体の方々が着実に続けてこられたことが、今回の「地方創生2.0」、「CCRC2.0」につながったのだと思います。






-scaled.jpg)