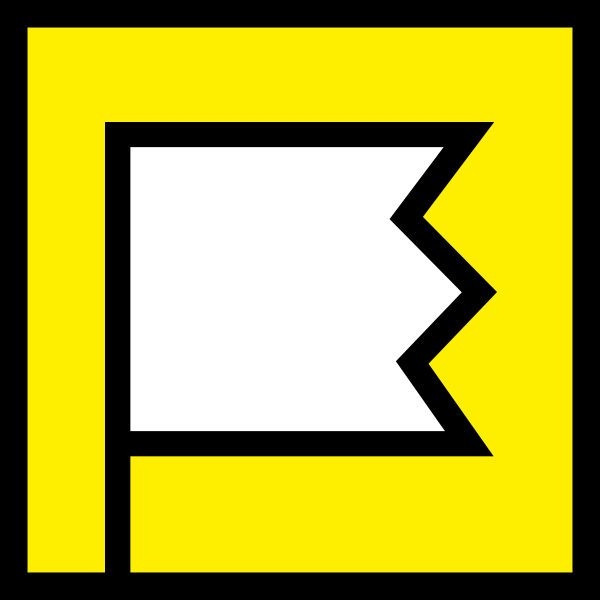News
今月のおすすめ本はシャルル・ぺパン著『フランスの高校生が学んでいる哲学の教科書』
.jpg)
日本で「哲学」を学ぶ場は限られている。小中学校では「道徳」、高校では「倫理社会」と、他の分野と合体して教えられるのはどうしてか。本書の第一弾となる『フランスの高校生が学んでいる10人の哲学者』と合わせて読むと、日本の教育界は、哲学を通して根源的な問いを発する若者の出現を恐れているのではないか。そんな疑いを抱かせるほど本書は面白い。
バチカン美術館に展示されているラファエロの『アテネの学堂』には、中央にプラトン(左の赤い服を着た人物)と弟子のアリストテレス(右の青い服を着た人物)が描かれている。プラトンが右手を上げているのは天に理想を、アリストレスが右手を前方水平に伸ばしているのは現実的な最善策を求めていることを表しているという。『~10人の哲学者』によると、師匠と弟子はこの点で対立していた。カントは「神の存在が証明されたら、私たちは神に祈らなくなる。私たちは善であり全能である神がいてほしいと願うことが『許されている』と考えた」そうだ。哲学と宗教は区別して考えられない。
第二弾である『~哲学の教科書』に入ると、個別のテーマ掘り下げられる。冒頭は「主体」だ。私は私だけでは理解できない。他者と向き合うことで隠されていた無意識が見えてくるし、行動を起こすことで自分の選択が正しいかどうかわかる。したがって考察だけではだめなのだ、ということをヘーゲルやデカルト、サルトルを引用しながら説いていく。「道徳」では「幸福」についてこう言及する。善行をなすこと、いやその前に善行をなそうと思うこと、思えることが重要なのであり、幸福になろうとすることではなく、幸福にふさわしい人間になることが大事なのだと。
哲学が観念に留まらない学問であることがよくわかる。『~哲学の教科書』後半の「キーワード解説」でもきわめて実践的な記述がなされている。細かくは本書を繙いていただきたいのだが、最後の章『バカロレア試験対策 実践編』(バカロレアとはフランスの国民教育省が管理する高等学校教育の修了を認証する国家試験)で哲学書は難しすぎると思っても読み続ける、わからなくても読み続けることが大切だと記していることを紹介しておこう。偉大なる哲学者たちが精魂込めて書いた作品が簡単に理解できるわけがない。それでも読み続けるという行為は「わからないことがわかる」ということではないか。
「哲学」を学校で教わってこなかったことは本当にもったいない。今からでも間に合う。読書のモチベーションが俄然上がってくる本だ。 (芳地隆之)