Topics
連載【8050問題を考える】第2回

今号では特定非営利活動法人KHJ全国ひきこもり家族会連合会本部事務局長の上田理香さんならびに楽の会リーラ・事務局長の市川乙允さんに登場いただきました。上田さんは、子どもや親がひきこもりで悩んでいる家族がその悩みを率直に語ることのできる場をとりまとめる役割を担い、その家族会連合会の東東京支部長である市川さんは、ひきこもり当事者の居場所づくりや就労支援も行っています。
お2人からは、ひきこもりの課題を解決するにはどのような地域社会が必要なのかという視点から話を伺ったのですが、はからずも、それは人と人との関係、ひいてはコミュニティとはどうあればよいのかという普遍的なテーマとなりました。
●「お互いに助け合いましょう」の標語がいらない社会に
特定非営利活動法人 KHJ全国ひきこもり家族会連合会
本部事務局長 上田 理香さん
(うえだ・りか)東京都出身。KHJ全国ひきこもり家族会連合会本部事務局長。家族相談士(日本家族カウンセリング協会認定)。親子二重の社会的ひきこもりを経て、2012年より事務局として従事。全国の家族会を立ち上げる。2013年より「ひきこもりピアサポーター養成研修派遣事業」を企画運営実施。現在、全国200名以上のピアサポーターが活動。家族の孤立を防ぐため家族支援の重要性を説き、長期高年齢化の相談事例に携わる。平成30年の厚労省自立相談支援事業従事者養成研修講師をはじめ、各地の行政機関、家族会での学習会、講演会も多数。

——KHJ全国ひきこもり家族会連合会はどういう経緯で立ち上がったのですか。
1990年に任意団体としてスタートしました。当時は「親の育て方が悪かったからひきこもった」「ひきこもっている子どもは甘えている」といった偏見に満ちていて、相談するところもありませんでした。そのため親もひとりで問題を抱えて、叫びだしそうなほど苦しみ、追い詰められているなか、家族会の創設者となる奥山雅久さんが、ひきこもりの子どもがいるとすべてをさらけ出したのです。その後、奥山さんは全国行脚を行い、各地に親の会が立ち上がりました。NPO法人化したのは2004年で、私は2012年から家族会にかかわりました。私にも母にもひきこもりの経験があります。ですから家族会での活動は自分自身を確認しながら進むことでもありました。
いまでも世間体を気にして悩みや苦しみを話せない方がいます。そこで私たちは、まずは調査を始め、その結果を国に伝え、実態を知ってもらう活動を始めました。そして、ようやく「ひきこもりの問題を社会全体で考えましょう」と認識されるところまできたのです。兵庫県明石市では中核都市としては初めて、ひきこもりに特化した相談窓口を設置しています。
当初、家族はひきこもり当事者を経済的に自立させようと考えていたのですが、「お金を稼いで一人で生きること=自立」ではありません。むしろ当事者にとっての課題は「人に頼れない」こと。ひきこもりは人との関係性を絶つことですから、仕事よりもまずは人間関係の回復を第一に考える。当事者が自分たちの声を発信し始めています。
——回復といっても一人ひとり違うと思います。共通するゴールはあるのですか。
自分自身が生きやすくなる、人や地域に受け入れられている感覚をもてるというところでしょうか。私たちは、ひきこもり当事者や家族だけでなく、いろいろな人が集まれる居場所づくりをしています。「自分はひとりじゃない、自分と似たような経験、生きづらさを抱えている人がいるんだ」ということを知って、孤立感を和らげていくことが大切なのです。
8050問題が地域社会を通して解決できるか、と言われれば疑問です。地域が活性化しても、ひきこもりはなくならないからです。地域がどんなに温かく、優しくても、人とのつながりを求められることがプレッシャーになることもあります。かといって、ひきこもり当事者が、たとえば人のいない離島に行けばよくなるかというと、そうではありません。
8050問題の本質は、困っている人が自らSOSを出せないこと、他者との関りを自ら断ってしまうことにあるからです。そこには自分が自分自身に向ける視線もあるわけで、負い目とか引け目、劣等感や罪悪感、自責感がないまぜになって孤立していく。そこに格差や貧困がかぶさってくるので、地域づくりとは何かと問われれば、格差や上下関係、貧困を感じさせるものが少ないコミュニティと答えたいです。
高齢者の孤立の要因のひとつは、当人が社会から必要とされなくなっていると感じることでしょう。「あなたの力がいつでも求められているんですよ」と、高齢者をお年寄りとしてみない、たとえば秋田県藤里町で行っている取り組みはひとつのモデルになるのではないでしょうか(人口3,500人弱、高齢化率45%を超える同町では、社会福祉協議会が地域拠点として「こみっと」を開設。介護予防の機能訓練室、食事サービスの調理室、カラオケや囲碁将棋を楽しむサークル室、婦人会や老人会などが開かれている。社協職員が「こみっと」を周知してもらうため、町内を戸別訪問した際、不就労期間が長く、家族以外との交流や外出がほとんどない18〜55歳のひきこもりが100人以上いたという)。
何歳になっても、いつからでも何かを始められる。そんな機会が増えてほしいと思います。大阪府豊中市では、都市型農園を拠点に人と人とがつながり、ふれあい、認め合い、支え合う共有空間を創造することで、社会参加を促進することを目指した「豊中アグリプロジェクト事業」が行われています。そこに集う人の多くは高齢の男性で、彼らは地元で採れた芋を焼酎にして売っていたりします。会社をリタイア後、家で肩身の狭い思いをしているお父さんたちの居場所にもなっているようです。
——その人一人ひとりに合った仕事を創っていくということがもっとあっていいと思います。
こういう仕事をしてもらうために人を育てます、ではなくて、仕事の方を細分化し、たとえば、障害や診断名の有無にかかわらず、その人が得意としているところ(苦手でないもの)が必ずあります。それを活かした働き方ですね。
ひきこもりは哲学者やイノベーターの面をもっている。社会が気がつかないこと、欠けていることを投げかけてくれるので、そうした能力を生かせるような社会になってほしい。大人向けの数学教室をやっている元ひきこもりの人もいるんですよ。「どうして大学の勉強を小学校でしちゃいけないのか」とか「どうして教科書は一律なのか」とか、自分がおかしいと思っていることに「なぜ?」と問いかけられる人たちもいて、なかには起業するケースもあります。
また、地域で孤立を防ぐためには、対人関係が負担な人でも安心できる環境づくりや、多様な働き方づくりを地域で開拓していくことが必要だと思います。「会話は苦手だけど、自分のペースでじっくり取り組めるものがあればいいな」という希望も少なくありません。在宅でできるものや、地域の困りごとのお手伝いなど。たとえば、ペットの世話、草取り、お掃除、農家のお手伝い、お弁当宅配、買い物の手伝いなど、コミュニケーションが苦手でも取り組めるもので、たくさんの選択肢があることが求められています。そして何よりも、「(ひきこもっている人を)困っているから助けますよ」ではなく、「あなたの力を貸してほしいんだけど」という特別視しない姿勢が大切だと思います。
——全国でも自殺発生の少ない徳島県の旧海部町に入ってフィールドワークを行った岡檀さんの著書『生き心地の良い町』(講談社)によると、同町には「病は市に出せ」という言葉があって、困っていることはオープンにして、みんなで解決策を考える。普段の関りは濃くなくても、弱みを見せれば誰かが助けてくれる成熟した人間関係が成り立っているそうです。
精神科医の森川すいめいさんが書いた『この島の人たちはひとのはなしをきかない 精神科医、「自殺希少地域」を行く』(青土社)にもそうしたことが書かれていました。手を差し出す側に「してあげますよ」という恩着せがましさはなく、かといって無視するわけでもない、「適度なおせっかい」があると。そういう地域には「お互いに助け合いましょう」なんていう標語はないんじゃないでしょうか。これからの地域は、各自がいろいろな共通項でつながれる、ゆるやかな関係性をつくっていく必要があると思います。
●地域で暮らす安心が家族間の信頼を育んだ
特定非営利活動法人楽の会リーラ
副理事長(事務局長)市川 乙允さん
(いちかわ・おとちか)サラリーマンで営業職を経験の72歳、ひきこもり主婦の父親。娘の不登校を契機に親の会に関わり、広島での親の会設立を経て、2001年KHJ東東京支部(楽の会リーラ)設立。6年前から東京都北区で、不登校・ひきこもりの自主家族懇談会「赤羽会」設立に関わり、現在副会長としても、地域家族会支援をしている。

——楽の会リーラのこれまでの経緯を教えてください。
楽の会がスタートしたのは2001年。同会はひきこもりの子どもをもつ親の組織で、私が副会長を務めました。その後、2005年にNPO法人社会参加センター「リーラ」という、ひきこもり当事者の居場所や就労の支援機関を立ち上げました。私が初代理事長として運営していたのですが、6年前に「リーラ」が「楽の会」を統合し、親と当事者の双方を支える現在のNPO法人楽の会リーラとなっています。
楽の会リーラではカフェも運営しています。喫茶店形式にしたのは、普通の「居場所」では、事前登録が必要など、入りづらいから。カフェなら、ひとりでふらっと来ることができる。さらに敷居を低くするため、交流コーナーとカウンターの両方のスペースをつくりました。
——居場所がほしい人にとっては、「居場所」と名づけられると、かえって来づらくなりますよね。
来訪者の8〜9割がひきこもり当事者、それ以外は家族や支援者、行政の方々です。カフェスタイルが珍しいのでしょう。水曜日と金曜日が13時から17時、木曜日は18時30分から20時30分、日曜日はおやじの会、女子カフェなどイベント的なことを開催しています。カフェでは就労体験の一環として当事者にボランティアとして手伝っていただき、ひきこもり等を経験したスタッフが曜日ごとに入るというシフトです。
——おやじの会では何をしているのですか。
ひきこもりの子どもをもったお父さん限定の集まりで、毎回5〜6人がやってきて課題を話し合うのです。おやじ同士でなければ話せないこともありますので、私やスタッフがファシリテーター役になって、愚痴なども全部吐き出してもらったり、経験談を話してもらったり。そのあとは飲み会に変わり、それには誰でも参加できます。おやじの会の参加費500円、懇親会(飲み会)500円。1,000円で結構充実した集まりになるんですよ(笑)。
——自分の悩みをさらけ出すのは難しくないですか。
私個人でいえば、たいへんでした。娘が学校に行かなくなったとき、わけがわからなかった。「ひきこもり」という言葉もなく、「不登校」とか「登校拒否」と呼ばれていた時代です。妻がしっかりしてくれていたので助かりました。そのころから私は地域に入っていこうと思うようになりました。
——それまでは仕事、仕事の人生だったとか。
私は静岡県浜松市出身で、かつては外資系の医療機器メーカーの営業職で転勤の連続でした。そうしたなかで娘がひきこもってしまったのです。当時は「なぜだ」「どうしてだ」と私も悩み、苦しみました。それが娘をさらに悩ませ、苦しめることになったのですが、いまから25〜26年前、不登校の若者たちをイタリアのトスカーナ地方で45日間、共同生活して農業体験してもらうという、ある団体の企画を知ったのです。
イタリア側には日本人のホスト役である宮川秀之さんという方がいました。彼はカーデザインで名をなした方ですが、イタリア人の奥さんとともにトスカーナ地方で農場をつくり、そこでグリーンツーリズムを始めていたのです。現地では精神科医や臨床心理士のケアがあり、イタリア語のできる日本人女性が生活面のサポートもしてくれるという。当時18歳だった娘は他の5人とともに参加したところ、とても元気になって帰ってきて、それから宮川さんとの交流が始まりました。そして、しばらくすると宮川さんから「あなたは会社人間で終わっていいのか」と問われ、私は地域に入ることを決心させられました。52歳のときです。
——お住まいはどちらですか。
東京都北区田端に30年以上暮らしています。自分が暮らす場所には挨拶のできる人がたくさんいた方がいい。自分の住んでいるところが楽しくないとつまらないと思っています。そうして自分の人生が充実することで、娘との距離が測れるようになりました。その後、彼女は結婚して近所に暮らしており、いまではどちらかが困ったときには手を差し伸べられる関係になっています。
——東京では急速に高齢化が進み、しかも単身世帯が増えていきます。
いまは地方の方がクルマ社会になっており、人との関係が疎遠になっているのではないでしょうか。私たちが住む北区田端のようなところの方が人との結びつきが強くなっているように思います。私たちはマンション住まいですが、周囲の一戸建ての住民の温かさも感じるし、お互いに支え合う、とてもいい関係です。
お互いに挨拶できる関係があるのとないのとでは、たとえば自然災害で避難所に行ったときに全然違います。40年以上前になりますが、当時住んでいた静岡県で七夕豪雨(1974年7月7日に台風8号の影響により静岡県全域で浸水害をもたらした集中豪雨)に遭いました。川の堤防が決壊する直前、真夜中に近所の7家族と一緒に体育館に避難したのですが、普段から付き合いがあったおかげで、3日間助け合い、不便さを感じませんでした。
——親が地域で安心して暮らすことが、子どもとの関係にもいい影響を及ぼしたということですね。
安心感は信頼へとつながります。まずは相手を否定しないで受け止める。それが「ひきこもっていてもいいんだよ」という子どもへのメッセージになります。親が子どもを信じ、応援するという関係ができれば、当人はゆっくり、ゆっくり回復していくのです。安心のエネルギーがたまっていくのでしょう。そうして双方が閉ざされた共依存関係から脱して、距離感を保てるようになるのだと思います。そうした人間関係は地域を再生させるヒントになるかもれません。
(聞き手/芳地隆之)
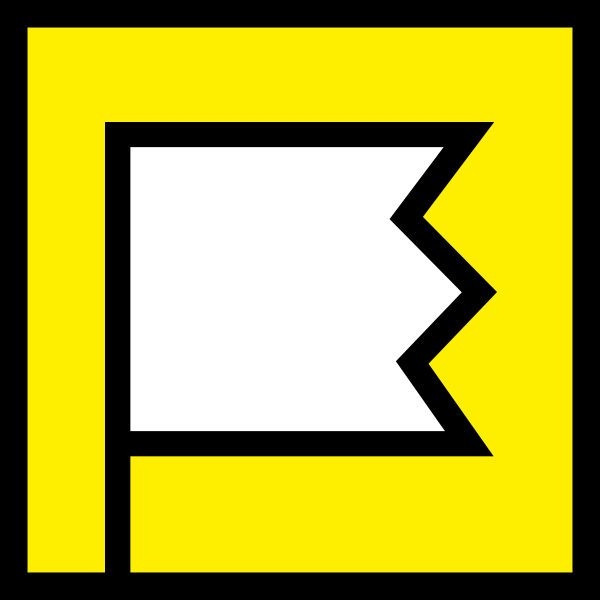





.jpg)