Topics
『ひとり親家庭』(赤石千衣子著/岩波新書)

著者であるNPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむの赤石千衣子理事長に会いにいったことがある。朝日新聞の記事「(あすを探る 家族・生活)ひとり親、移住後も支援を」(2017年3月30日付)が気になっていたからだ。東京一極集中を是正し、地方の人口減少に歯止めをかけるため、2014年から政府が掲げる地方創生において、シングルマザーが注目されるようになった。過疎が進む地方にとって、彼女たちは子どもと一緒に来てくれるし、もしかしたら人手不足の介護職についてくれる、あるいは地元の独身男性と再婚してくれるかもしれない、ありがたい存在なのである。少子高齢化が続けば消滅してしまうことへの危機感からの発想だが、シングルマザーの移住を増やしたいのであれば、まずは地元にいるシングルマザーが生きやすいまちをつくるのが先決という視点が欠けている。「ひとり親家庭や子育て世帯に移住を促したいのであれば、ひとり親や子育て家庭にとってナンバーワンの地域となることだ」との著者の言葉に私は大いに頷いたのであった。
本書は、多くの当事者(ひとり親、その子ども)の声(ときに読んでいて胸が苦しくなる)を紹介するとともに、ひとり親家庭の貧困について、国の政策、地域や家族、ジェンダー、虐待など様々な側面に光を当てながら、読者が問題を整理し理解できるよう導いてくれる。「母子家庭の母親は怠け者で不道徳で福祉依存だ」という社会の偏見には、日本のシングルマザーの就労率は80%以上と世界のなかでも高い事実を挙げて反論。子どもの貧困率がほとんどの国では再分配後、再分配前に比べて大きく減少しているにもかかわらず、日本はその差がほとんどなく、政府の再分配機能の大きさからいうと、ギリシャ、イタリアに続いて下から3番目であるとの指摘は、人間は生まれながらに平等であるならば、生まれた環境によってその人の一生が左右されてはならない——という考えを基本とした制度設計がなされるべきだとあらためて思わせる。
ひとり親のためだけではない。著者が引用する、NPO法人キッズドア(塾に行けない子どもたちに無料の学習支援を行う)の渡辺由美子代表の「貧困にさらされる子どもたちが将来仕事に就き、中小企業の正社員になったとすれば生涯で平均3010万円の税金を払うだろう。他方生活保護受給者になれば、35年間で3360万円を社会が負担することになる」のように、その境界線のどちらにいるかで、世の中は大きく変わるのだ。どのような暮らしをしている人にも、当事者性をもって読んでほしい書である。
(芳地 隆之)
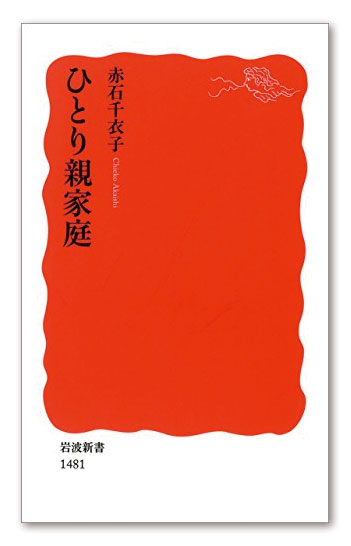
(赤石千衣子著/岩波新書)
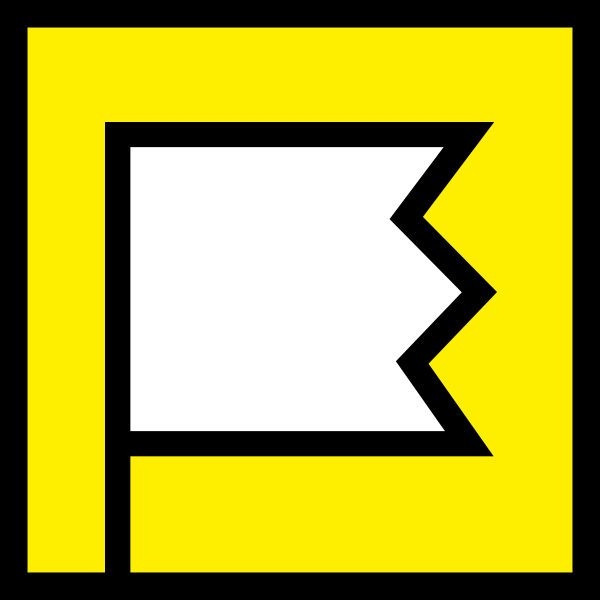



_page-0001.jpg)
.jpg)
