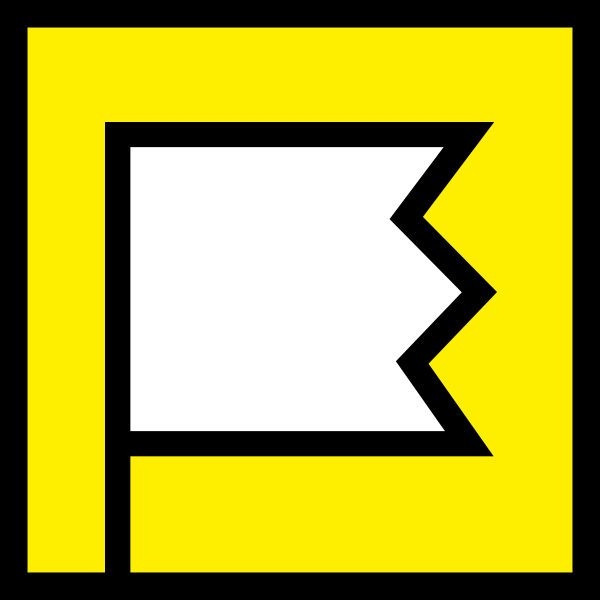Topics
『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』(著者 ジリアン・テット 土方奈美訳/ 文春文庫)

カンパニー制という経営組織体制がある。企業の事業部門を分社化し、各々が独立性をもったひとつの会社として経営を行うのだが、それが落とし穴になってしまった例として、著者はソニーを取り上げる。1999年11月にラスベガスで開催された見本市「コムデックス」で、当時の出井伸之社長はインターネット時代のデジタル音楽プレーヤーを3つ発表。画期的な新商品が3つも、と驚嘆で迎えられた。しかし、互換性のない独自の技術によって開発された各商品は競合関係になって淘汰され、同社はデジタル音楽市場から後退していく。主役は「iPod」を擁するアップルにとって代わられた。
書名のサイロとは農産物、家畜の飼料を蔵置・収蔵する倉庫や容器のことを指す。各人が自分の専門のなかに閉じこもったままの状態を表する言葉だが、日本語でいえば「たこつぼ」だろうか。「ほうれんそう=報告・連絡・相談」の徹底をうたう企業はあるが、上司(本社)と部下(現場)との情報共有を重視するための慣習はややもすると縦割りを助長する。
アップルのスティーブ・ジョブズは、サイロが「管理職に未来に飛び込むより既存の製品アイデアや過去の成功にしがみつこうとするインセンティブを与える」とし、プロダクトラインの境界を取り払った。
シカゴ警察で殺人予報地図を作成したのは、地元のIT企業で仕事をしていたブレッド・ゴールドスタインである。9・11にショックを受けた若手ビジネスマンが、凶悪犯罪が頻発する大都市の警察という、これまでの職場環境とは真逆の分野に飛び込んだことで生まれたものだ。
著者は文化人類学者であり、中央アジアのタジキスタン共和国でフィールドワークなどを行った後、フィナンシャル・タイムズのジャーナリストに転身した。そこで部署横断的な組織運営の重要性を見出したのである。サイロを否定しているのではない。互いがオープンに影響し合うことで新しいものが生まれるためには、アウトサイダーの視線が不可欠なのだ。
ちなみに東京帝国大学医学部を卒業し、内科学、血液学の専門家として原爆投下後の広島における日米の実態調査団に加わった加藤周一はその後、フランス留学を経て、芸術や文化、社会など多様な批評活動を展開する。加藤は自叙伝のなかで、自分は非専門の専門家を志したと振り返っている。
サイロをまたがる「非専門の専門家」は、行政、民間事業者、住民などの利害が複雑に絡まり合う地域にあって不可欠な存在になるはずだ。
(芳地隆之)
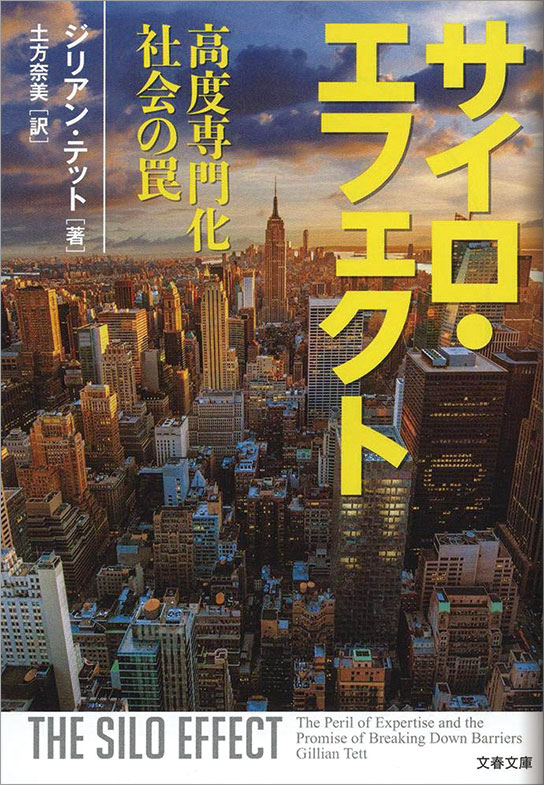
(著者 ジリアン・テット 土方奈美訳/ 文春文庫)